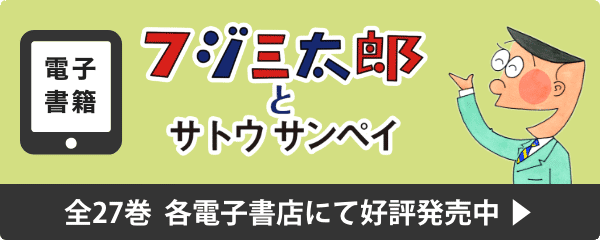固定席なくす「フリーアドレス」 本当に働きやすいのか
オフィスに固定席を設けない「フリーアドレス」の導入を進める会社が増えているらしい。従業員間のコミュニケーションを促したり、コスト削減につなげたりするのが目的だが、落ち着いて仕事ができそうにないと疑問を抱く人もいるようだ。
先進的な取組みに賛否両論
会社のオフィスといえば自分専用の机と椅子があるのが当然、というのは一昔前の話。いま注目のフリーアドレスのオフィスでは固定席がなく、ロッカーからパソコンなどを持ち出して共用スペースの空いている席で仕事をする。
このようなオフィススタイルはIT技術の発達を背景に、ユニクロやIBM、コクヨなど大手企業を中心に導入が進行中。2010年8月2日に六本木ヒルズに移転したグーグル日本法人でも採用されている。
ねらいは、従業員間のコミュニケーションを活性化させ、仕事の生産性を上げようというもの。ペーパーレス化によって執務スペースが縮小できたり、コスト削減が進んだりする効果もあるようだ。
10年9月1日朝に放送された日本テレビ系「ズームイン!!SUPER」の紹介によると、カゴメでは、執務スペースの縮小によって打ち合わせ用スペースを5倍に拡張。コンサルティング会社シグマクシスでは、全従業員280人でプリンター1台を共有しているという。
このような先進的な取組みに、ネット上には羨望の声が上がっている。
「フリーアドレスいいなあ!面白い」
「自由なオフィス環境だと、発想も自由になるよね」
「いまの職場は暗くて堅苦しい。グーグルうらやましすぎる」
一方で、フリーアドレスの効果に疑問を持つ人たちも。
「なんの意味があるのか分からない。固定席で何が悪いのか」
「私は嫌。落ち着かない!できればパーティションで囲んでほしい」
確かに固定席がなくなることで、さまざまな戸惑いが生まれそうだ。顔と名前を一致させにくくなり、かえってコミュニケーションが取りにくくなる人もいるだろう。実質的な「指定席」が生じて形骸化するのではという懸念もある。
「ワークスタイルの変更」がカギ
しかし実際に運用する会社では、試行錯誤しながら答えを出しているようだ。NECネッツエスアイでは、2年前から営業部門と技術部門の一部でフリーアドレスを導入。11年10月には社屋移転に伴い、3000人を対象とした全社導入を図る。
移転には15億円の費用がかかるが、賃貸面積を4割近く削減でき、年間10億円のコスト削減を見込んでいる。
同社コーポレートコミュニケーション室の福島徹氏によると、フリーアドレスの効果を上げるには固定席をなくすだけでなく、情報通信技術(ICT)を活用しワークスタイルの変化に対応できるインフラを整えることがポイントになるという。
「固定席をなくすためには、業務を完全ペーパーレス化する必要があります。そのためには、打ち合わせスペースに自分で作った資料をすぐに投影できるネットワーク環境やプロジェクターなどが必要になるのです」
資料作成やプログラミング、打ち合わせなど、日々の仕事の内容に応じて作業スペースを柔軟に変えていくことで「指定席」は生じなくなる。
一方で、全社導入にあたって総務や経理、人事などの管理部門では、実質的な指定席をあえて残す。「管理部門の人たちがどこにいるのか分からずに探してしまうようでは、かえって生産性が下がりますからね」
要するにフリーアドレスは、働き方を変えずに導入すればやりにくいところも出るが、インフラや働き方を一気に変えると、さまざまな効果が出る可能性があるようだ。