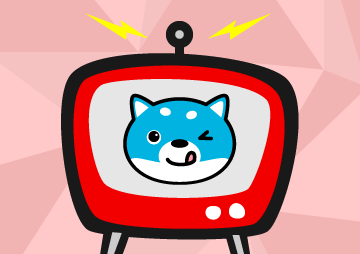【取材秘話】球児たちの激闘が大会規則を変えた
取材秘話・フラッシュバック(5)
高校野球の延長戦は独特な悲壮感に満ちて劇的なドラマを生む。夏の選手権に限っても幾つもの名勝負が時代の節目になった。
近年はその土が甲子園の土産物になった感がする。負けたチームの選手は涙の乾く間もなく、ベンチ前でシューズ袋に砂を詰め込む。全員が砂採り作業に没頭する光景は今やお馴染みの光景になった。
大会初の延長戦は1915年(大正4年)の第1回大会決勝で秋田中対京都二中が対戦、13回裏に京都二中が1点を取り3対2でサヨナラ勝ちしている。もっとも豊中球場での出来事だ。甲子園球場での伝説的な延長戦となると33年(昭和8年)の第19回大会で明石中と中京商が渡り合った25回の死闘だろう。明石中の中田武雄、中京商の吉田正男の白熱した投手戦は0対0のまま延々と続き、25回裏に中京商が四球を足場に無死満塁とし、続く大野木浜市のゴロを明石中の二塁手嘉藤栄吉が本塁へ悪送球、4時間55分の試合が決着した。嘉藤は後日、そのときの心境を、「大変なことをした。明石に帰ったら殺される。死を覚悟した」と話した。ところが明石駅に着くと大歓迎を受け、自宅まで提灯行列で送ってもらったそうだ。「一生懸命にやると人様にも分かってもらえるんですね」としみじみ言ったものだ。投球数は吉田が336球、中田が247球だった。
激闘は健康管理にも影響を与える。58年(昭和33年)の第40回大会では準々決勝で徳島商・坂東英二と魚津・村椿輝雄が18回を0対0で譲らず、この夏から設けられた「特別規則第13条」により、18回で引き分け再試合となった。翌日の再試合は徳島商が3対1で勝利。このとき「泣くな村椿」とファンは小さな大投手の村椿をねぎらった。
その後、99年12月には高野連の全国理事会で「18回を15回とする」再改定があった。
開幕戦がいきなり延長戦で引き分け再試合というのもある。64年(昭和39年)の東京五輪の年、第46回大会で掛川西と八代東が18回、0対0で引き分け、再試合で掛川西が6対2で勝った。
神様が創った試合といわれる79年(昭和54年)第61回大会の箕島対星陵は、星陵の一塁手が転倒して落球、2度の同点本塁打ともつれにもつれ、箕島が18回裏にサヨナラ勝ちした。
平成になってからは、98年(平成10年)第80大会の準々決勝で横浜対PL学園が延長17回までもつれ、横浜が9対7で勝利、松坂大輔の熱投が話題を呼んだ。2006年(平成18年)の第88回大会決勝、駒大苫小牧対早稲田実は15回1対1の引き分け、再試合は4対3で早実が勝ったが、苫小牧・田中将大と早実・斎藤佑樹が力投。斎藤は2試合とも完投した。
延長戦は体力の負担が大きく、大会はその都度、選手の健康管理に重点を置いた回数に改定されてきた。(敬称略)
岡田 忠
岡田 忠(おかだ・ちゅう)プロフィール
スポーツジャーナリスト。1936年広島県生まれ。立命館大学卒。朝日新聞社東京本社編集委員を96年に退職して現職。高校・大学では野球部に所属し投手をつとめる。高校野球のテレビ解説経験も豊富。