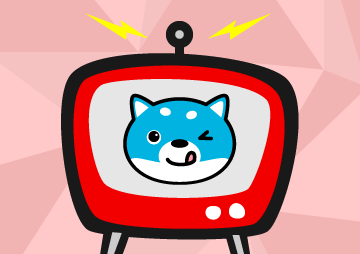没後10年「岡本喜八監督」戦争映画に若者の共感!「自分たちももしかしたらああなる」
10年前に81歳で亡くなった東宝の岡本喜八監督が自ら脚本を書き監督した戦争映画が若い人たちに共感を呼んでいる。「独立愚連隊」(1959年)など、末端の兵士たちの活躍を痛快アクションを織り交ぜてコミカルに描いた作品が特徴だが、作られた当時は岡本監督が思いを込めた戦争の愚かさや軍隊の非人間性は必ずしも伝わらなかった。戦死者を冒涜するものだとの批判のなかで、観客が共鳴したのは娯楽映画として支持だったという。
それがいま、大学では学生が主催して鑑賞会まで開かれている。東京・渋谷で上映された「独立愚連隊」を見た若者がこんな感想を漏らした。「それなりに一生懸命生きているけど悲惨な目に遭うという見せ場が、衝撃だった」「ユーモラスで明るく描いているので、逆に普通の戦争映画よりも本当にリアルな感じがした」
「英霊たちの応援歌、最後の早慶戦」を見た男性会社員(26)は、特攻隊の若者たちが出征前に最後の宴会を開くシーンが忘れられないとこう話した。「戦争があった時代に、普通に生きてきた人たちもいた。自分たちも、もしかしたらこういう結果があるのではないか。僕たちも近いところを感じる」
「戦争は悲劇だった。しかも喜劇でもあった」笑い飛ばすことで描いた理不尽
岡本監督が映画界入りしたのは戦争真っ只中の19歳の時だった。「映画は面白くなければダメだ」が持論だったが、映画には自らの体験が深く影響している。映画会社に入ってすぐに軍需工場に徴用され、さらに「特攻要員」として陸軍予備士官学校に送られた。
敗色濃い戦争末期の8か月間を兵隊として送り、目の当たりにしたのは爆撃によって殺される20歳前後の若者たちの悲惨な姿、栄養失調や特攻訓練、死への恐怖という過酷な現実だった。
そんな中で岡本監督が考えたのが、「刻々と近づく死への恐怖・・・そんなある日、はたと思いついたのが、自分を取りまくあらゆる状況をコトゴトく喜劇的に見るクセをつけちまおうということである」(岡本喜八著『マジメとフマジメの間』)
辛うじて生き延び、映画界に戻って監督2年目に手掛けたのが「独立愚連隊」だった。敗色濃厚な中国戦線に送り込まれたはみ出し兵士たちが活躍する痛快なアクションとコミカルなストーリーで、当時の戦争映画の常識から外れた破天荒な作品だった。岡本監督は「戦争は悲劇だった。しかも喜劇でもあった。だから喜劇に仕立てバカバカシサを笑いとばす事に意義を感じた」(『マジメとフマジメの間』)と述べている。
その後も、中国大陸の戦場を舞台に次々を「兵隊」を主人公にした作品を制作したが、監督9年目に取り組んだのが「日本のいちばん長い日」だった。戦争終結を伝える玉音放送を阻止しようとする軍部と政府の攻防を描い作品で、大ヒットして数々の賞も受賞したが、岡本は内容にはまったく納得ができず、末端の兵士を描かなかったことに罪の意識を感じていたらしい。
妻の岡本みね子さんは当時の監督について述懐している。「いくら努力しても一等兵にもならない人がみな死んでいったと言っていた。そこを一番描きたかったんだと思います。映画監督をやめないといけない気分になるとも言っていました」
当時の監督の思いを綴った手記が今回初めて公開された。次の作品となる「肉弾」の制作スタッフに宛てて書いたもので、タイトルは「肉弾とあいつ―その心情と眞意」だ。『肉弾』は特攻が決まった主人公「あいつ」の1日限りの休日を通して描いた作品だ。手記には「『日本のいちばん長い日』の欠落した部分を肉弾でうめねばならぬ」「肉弾は岡本そのものだ」とあり、作品に込めた思いについて「私の目の前で死んだ12人の戦友もフィリピンでもくずと消えた25名の同窓生も夫々小銃弾であった。二度と小銃弾になってはならない」と書いている。