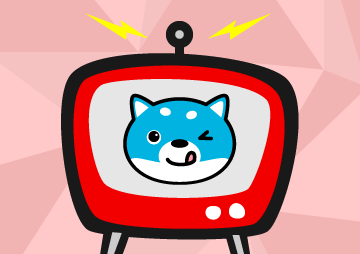「雅子皇后と紀子妃」どうしても喧嘩させたいらしい週刊文春と週刊新潮――勘ぐり過ぎじゃないの
前にも書いたが、このところ秋篠宮家に対する批判が週刊誌に目立つ。週刊新潮は、雅子皇后と紀子妃が「冷戦」状態だと報じ、週刊文春は、長男・悠仁さんに対する「刃物事件」があったのだから、クラスメイトやその保護者、学校に謝罪コメントを出すべきではないかという上皇后の考えに対して、秋篠宮は「悠仁が悪いことをしたのではないのに、なぜ謝罪文を出さなくてはいけないのか」と、これを聞き入れなかったと報じている。
週刊新潮は以前から紀子妃に対しては厳しい見方をしてきているが、今号では、皇嗣家になって職員の数も増えたのに、相変わらず彼らへの"ご指導"は苛烈を極めているというのだ。
また、先ごろテレビの某ワイドショーで、小室圭の代理人の弁護士が「本人は弁護士になるとはいっていない」「彼はいまライフプランを作っている」などと発言し、「眞子さんとの結婚は諦めない」ととれるニュアンスがあったことを知らされて、<「まさしく怒髪天を衝くようなご様子でした」(秋篠宮家の事情に通じる関係者)>というのである。
何をそんなに怒るのか、私にはわからないが、眞子さんの結婚問題、佳子さんの母親への反発、悠仁さんの警備や帝王教育のやり方などが重なって、紀子妃の心を欝々とさせているようだ。
さらに、週刊新潮によると、「雅子さまが皇后となられる日が決まって、妃殿下は内心面白くないのだろう」と、宮廷職員の間では囁かれているというのである。
雅子妃は男の子に恵まれず、その後も体調を崩し、公務を休むことが多くなった。その間に紀子妃は男の子に恵まれ、雅子妃の不在を埋めるために公務にも邁進してきた。一時は、皇太子家よりも秋篠宮家のほうがメディアへの露出も多かった。それが、御代替わりで一転してしまったから、紀子妃の内心穏やかでないというのだが、あまりにも勘繰り過ぎではないか。
5月22日(2019年)に、日本赤十字社の名誉総裁として、雅子皇后が初めて「全国赤十字大会」に出席するが、その際、紀子さんたち女性皇族たちが雅子皇后に"つき従う"形で式は進行するという。
<「一般出席者の前で皇后さまにお辞儀などの挙措をなさる際、紀子妃殿下の御胸中には、どのような思いが去来するのか......。さぞ複雑であろうと拝察いたします」(宮内庁関係者)>
こうやって、雅子皇后VS.紀子妃の対立が創り上げられていくのだ。怖いね、週刊誌は。
勉強好き悠仁さん―東大に入れたい父親・秋篠宮は教育パパ!推薦制度を考えているらしい
週刊文春のほうはさらに深刻である。秋篠宮家長男を刺そうと中学校に侵入した長谷川薫容疑者のために、お茶の水女子大付属中は、連休明けも休校が続き、5月11日には臨時の保護者会が行われ、紀子さんも参加した。週明けの13日からようやく授業が再開された。
秋篠宮は皇嗣になっても警備体制はこれまで通りにしてほしいと望んでいるようだが、長男の警備はそうはいかないのではないか。またぞろ、学習院に通っていれば、こんなことにはならなかったという声があるというが、それはともかく、警備体制は早急に再点検されるべきであろう。
以前から、秋篠宮夫妻は長男を東京大に入れたいという希望があるといわれる。秋篠宮は東大総合研究博物館で特別研究員を務めているし、長女も同特任研究員の肩書を持っている。
長男の昆虫好きは知られているが、最近では「解剖学」にも関心を持っているといわれる。伝えられるところでは、知識欲が旺盛で、昭和史の研究者の半藤一利を招いて昭和史の勉強もしているそうだ。秋篠宮は東大の推薦制度を使って東大に入れたいという青写真を持っているそうだが、このままいけば問題はないのではないか。
これまでの天皇は、父の在り方を見て帝王学を学んできたが、秋篠宮が天皇即位を拒否すれば、皇太子としての準備期間も与えられないまま、悠仁は即位しなければならなくなる。週刊文春のいう通り、たしかに秋篠宮家にとって重い課題であることは間違いないだろう。
「令和」選考の大役務めたある内閣研究官――30年間調べつづけて改元見ないまま孤独死
毎日新聞は4月1日、WEB上で「新元号『令和』考案者は中西氏か」というスクープを放った。高志の国文学館(富山市舟橋南町)の中西進館長も、明言はしないが考案したのが自分であることを否定していない。見事なスクープだったが、その情報を取るために、2011年から新元号を追いかけて極秘取材してきた記者たちの地道な努力があったことを、毎日新聞政治部の野口武則が週刊文春で明かしている。
興味深いのは、次の元号を何にするかという大役を担ったのは、内閣官房副長官補室の肩書を持つ尼子昭彦という人物だったということだ。彼は漢籍の専門家で、独立行政法人国立公文書館統括公文書専門官室主任公文書研究官 内閣事務員という長い肩書があり、野口によれば、「元号研究官」だったという。
多くの元号を選んでもらう学者たちに会いに行っていることはわかったが、杳として彼の所在はわからなかった。記者たちが回った学者たちも、尼子が訪ねて来たことを認めた。内閣官房幹部は尼子が書いた雑誌記事を見せると、「とうとう見つけてしまったのか」と呻いたそうだ。だが、尼子を知る関係者も「真面目で口数が少なく、同僚と飲みに行くこともなかった。漢籍だけが生き甲斐だった」と語るだけだった。
60歳の定年直前に公文書館を退官して、内閣官房に「特定問題担当」として再任用され、非常勤で元号担当を続けていたそうだ。昨年の秋、取材班はようやく尼子の自宅を探し当てたが、住んでいたのは別人だった。
管理人は、18年5月19日、一人暮らしの尼子が出勤しないため、後輩の内閣官房職員が訪ねてきて、亡くなっているのを見つけたという。病死だった。平成の30年間、元号一筋で取り組んできた彼は、改元を見ることなく逝ってしまったのである。悲しくもいい話だ。
高田純次 ポルシェで当て逃げ?咎められたら20万円出して「これでナッシングにして」
ガラッと変わって、高田純次(72)の"当て逃げ"の話。私は、テレビ朝日系で朝やる高田の「じゅん散歩」のファンである。地井武男、加山雄三に続いて三代目だが、とぼけた味がなかなかいい。もともとサラリーマンだったが、1977年に劇団東京乾電池に入団し、ジワジワと人気を上げてきた苦労人のようだ。
その高田がクルマ好きで、ポルシェ・カイエンなどの高級車を乗り回していることは知られている。その彼が、4月14日、首都高でA(22)が運転するクルマにぶつかったという。その上、そのままスピードを上げて走り去っていこうとしたというのである。
Aはそのクルマを追いかけた。首都高を出て一般道の赤信号で止まり、ラフな格好で高田がクルマから出てきたという。高田は開口一番「何ですか?」といった。驚いたAが「このクルマに当たりましたよね」というと、「当たってませんよ」と完全否定した。
後から駆け付けたAの父親が高田だと気づく。事故後に病院へ行ったAは、「頸椎と腰椎の捻挫で全治2週間」と診断されている。Aに高田は、破損部分は全部直す、今20万円持っているから、これでナッシングにと持ち掛けたという。
結局、2時間以上経過して、高田は警察に通報した。別れる際、体に異常をきたした場合は、保険で対応できない分は話し合いをしようと、一筆書いて渡したそうだが、後日、代理人の弁護士から、大した事故ではないから治療費は出せないという電話が入った。その後、高田に連絡の電話を入れたが出ないという。
週刊文春の取材に対して、高田のマネージャーの対応もいただけない。高田も週刊文春の直撃に、Aの運転が危ないのでひと言いってあげようとした、20万円でナッシングにしてくれなどといっていないと抗弁した。だが、Aはスマホで高田とのやりとりを録音していて、そこにはっきりと高田の「ナッシング」という言葉が残っていた。
週刊文春によると、高田はこの10年ですでに2回も事故を起こしていたという。高田に高齢者ドライバーだという意識があるかを問うと、「まあ、自分で危ないなと思うことはほとんどないんですけどねえ。(中略)ただ、まあ世間一般で高齢者のアレが多いということで、七十歳以上で、高齢ですから、今後どうするのかってことはありますね」といっている。事故を起こしても「テキトー」「無責任」ではファンが離れるぞ。
高田は、滋賀県大津市で園児2人がひき殺され、1人が意識不明の重体になった事故で、亡くなった園児・伊藤雅宮(がく)ちゃんの父親の言葉をどう聞くのだろうか。
この事故で、直進していた軽自動車を運転する61歳の女性と、右折車の新立文子容疑者(52)が逮捕され、直進車の運転手は夜に釈放され、「前をよく見ずに右折し、衝突音で初めて対向車に気がついた」と供述した新立は自動車運転処罰法違反容疑で逮捕された。
雅宮ちゃんの葬儀には、入りきれないほどの列席者が集まったそうだ。父親は気丈に振る舞っていたが、母親は遺影を抱えて声を上げて泣いていたという。父親は4歳上の姉の手紙を代読した。そこには、「お別れじゃないよ、私とパパとママの心の中にいるよ。いつもケンカしていたけど、ほんとうは好きだよ」と書かれていた。
父親は、これだけは世間に伝えたいと、こう語ったという。「お願いです。私たちのような悲しい思いをする人が減りますように、ハンドルを握る時には雅宮のことを思い出し、安全運転をお願いします」
殺人事件では、2人殺せばよほどの情状酌量の余地がなければ死刑になるのに、交通事故ではなぜ死刑にならないのか。お前は運転しないからとよくいわれるが、私には不可解でしょうがない。
私は昔、講談社の子会社のクルマ雑誌を出している会社へ出向させられた時、挨拶の冒頭、「クルマは人殺しの道具だ」といって顰蹙を買った。だが、運転する者は、そのことをいっときでも忘れてはいけないはずだ。私が間違っているのだろうか。