農林・水産業
現状と歴史
手厚い過保護行政に守られ、近代化に大きく立ち遅れ
日本人の主食は、昔から米と魚介類、野菜、豆が主体であった。 しかし経済発展にともなう食の“欧米化”によって、戦後は一貫して“米離れや魚離れ”が進み、その一方でパンや牛肉、豚肉などの消費が拡大してきた。

日本で最も有名なコシヒカリの産地である新潟県南魚沼市の水田
この欧米化の結果、日本は米や鶏卵、野菜、果実の一部以外は、すべて海外からの輸入に依存するという異常な状況となっている。日本食(和食)の主要な食材である魚や大豆や、養鶏の飼料も、大半が海外からの輸入に頼らざるをえない状況だ。日本の食糧自給率は2002年度には約40パーセントにまで低下、先進国の中で最低の水準となっている。
一方、供給する側である農家は、これまで国の手厚い過保護行政に守られ、農業の近代化に大きく立ち遅れてきた。農業従事者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となり、補助金漬けの農政のツケとして日本の消費者は国際価格の数倍もする高い米の購入を強いられてきた。
1988年に牛肉・オレンジ輸入自由化
そうした中で、国の内外から市場開放の要求が強まった。農産物の中では野菜、果実、畜産物の多くは80年代以前に輸入自由化されたが、牛肉・オレンジが自由化されたのは88年、主食の米に至っては国内の農業団体の抵抗が根強く、高率関税の付加と引き換えにようやく自由化に踏み切ることができたのは99年になってからである。
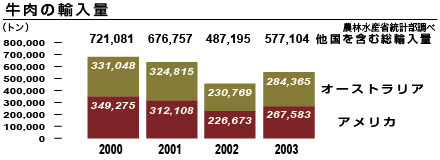
また日本は世界最大の水産大国でもあった。しかし最近では、若年層の魚離れ、商業捕鯨の禁止、米露中韓など周辺諸国との漁業協定の締結などによる漁労活動の制限によって、80年代後半には年間1200万トンを誇った生産量が、最近では700万トンを割り込んでいる。かつての面影はない。水産大国の地位を中国に明け渡して久しい。
将来を展望するための3つのポイント
ポイント1
株式会社の参入は農業の活性化につながるか
2000年11月に改正農地法が成立し、民間の株式会社が農業生産法人として農地の権利を取得できるようになった。これによって、実質上、これまで禁止されていた農業分野民間の株式会社の参入が認められた。今後は、花、野菜、青果、畜産、肥料、飼料、そして日本の農業の本丸である米のビジネスにまで、民間企業の参入が進む。そうなれば、農業分野にも遺伝子組み換えなどのバイオ技術の導入などが進み、日本の農業にも再び活力(=競争力)がよみがえってくる可能性がある。
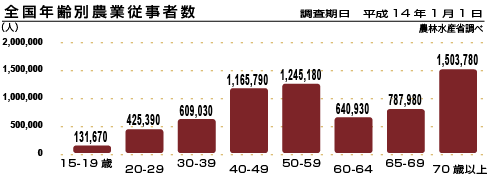
ポイント2
農協は生き残れるか
日本の農業保護政策の象徴であった「食糧管理法」は、第2次世界大戦時代の戦時体制を引きずりながらも、戦後の農業政策のバックボーンとなってきた。その実行部隊が農業協同組合(農協)だった。農協は遅ればせながら90年代から農協組織の広域合併などを進め体質改善に努めてきたが、農協系金融機関の破綻や大規模農家の農協離れなどで、農協の基盤沈下には歯止めがかかりそうにない。一部には農協の自主改革は限界があるとの見方も強い。民間の株式会社の参入と反比例する形で、農協の存在感はさらに後退していくことだろう。
ポイント3
加工・冷凍技術、バイオに活路を見出せるか
かつての日本の水産王国を支えたのは、マルハ、日本水産、極洋、ニチロ、宝幸水産の「水産5社」だった。大型の船団を擁し、内海、外界で大規模な漁労を展開する水産業者だった。しかし、商業捕鯨に禁止や周辺諸国の水産資源ナショナリズムの高まりなどを契機に、さしもの日本の水産会社も遠洋漁業から相次いで撤退せざるをえなくなった。
最近では、冷蔵・冷凍・真空保管技術とコンテナ化による物流革命の波にうまく乗ることができたニチレイ、東洋水産、加ト吉などの新興企業の躍進が著しい。こうした企業は、魚介類の冷凍・冷蔵保存業者として頭角を現している。かつての水産5社も漁労から撤退した後は、加工、冷凍技術を活用した総合食品商社として生き残りの道を模索しつつある。
また魚介類は本来、高タンパク低カロリーの食材であるのに加えて、DHAやEPA、キトサンなどの優れた栄養素を持つことが判明している。こうした水産資源の利点を、バイオ技術を活用して、消費者の健康志向に合致する形でうまく商品開発ができれば、水産業界も斜陽産業から大きな成長産業へと再び舵を切ることが可能になるかもしれない。

