両陛下はなぜ「水俣病胎児性患者」と面会したか 故・石牟礼道子さんと美智子皇后の「秘話」
2018年2月10日に亡くなった石牟礼道子さんは、水俣病に関心を持つ多くの人と深く交流した。美智子皇后もその一人だった。
天皇・皇后両陛下が水俣に行ったとき、極秘裏に胎児性患者と面会したことがあるが、それは石牟礼さんの願いが実ったものだった。
-
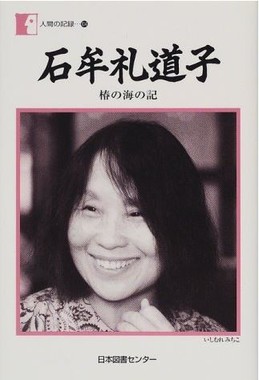 著書「石牟礼道子―椿の海の記」より
著書「石牟礼道子―椿の海の記」より
「絶対に極秘」直前まで患者にも知らされなかった
2013年10月27日、天皇皇后両陛下はそろって初めて水俣を訪問した。「全国豊かな海づくり大会」に出席するためだった。スケジュールは事前に公表されていたが、予定にない「面会」があった。両陛下に会ったのは、金子雄二さんと加賀田清子さん。ともに水俣病の胎児性患者で58歳。二人が過ごす福祉法人「ほっとはうす」の施設長、加藤タケ子さんだけが立ち会った。
胎児性患者は、「水俣病のまま生まれてきた赤ちゃん」ともいわれる。母親の胎盤を通った水銀で被害を受け、言語障害や運動失調など様々な症状を抱える。すでに亡くなった人も少なくない。存命の人もたいがい療養施設やケアホームで暮らす。水俣病患者の中でも最も悲惨な例として知られる。
「石牟礼さんから熱心にすすめられて、皇后陛下が胎児性患者にお会いしたいという強いお気持ちをお持ちです」――そんな急ぎの連絡が、県から施設長の加藤さんにあったのは両陛下が水俣を訪問する前日の朝だった。すべて絶対に極秘、と言われた。直前まで、実際に面会する金子さんと加賀田さんにも教えることができなかった。当日、面会会場の環境センター応接室に着くと、すでに両陛下が二人だけで座っていた。金子さんと加賀田さんは車いす。加藤さんが立ったままでいると、陛下から「どうぞお座りください」と正面の椅子をすすめられた・・・。大宅賞受賞のノンフィクション作家、高山文彦さんは著書『ふたり――皇后美智子と石牟礼道子』(講談社)でその様子を克明に再現している。
この面会が実現する少し前の7月、石牟礼さんは東京・山の上ホテルで開かれた社会学者の鶴見和子さん(1918~2006)をしのぶ会に出かけた。米国の大学や大学院で哲学などを学んだ鶴見さんは日本を代表する社会学者で、石牟礼さんとは共著も出している。その会には美智子さまも出席されていた。車いすの石牟礼さんは皇后の隣の席を用意され、2時間ほど親しく話した。「こんど(豊かな海づくり大会で)水俣に行きます」ということを直に聞いた石牟礼さんは、後日、「胎児性水俣病の人たちに、ぜひお会いください」と手紙を書いた。「この人たちは、もうすっかり大人になりまして、五十歳をとっくに越えております。多少見かけは変わっておりますが、表情はまだ少年少女です・・・」
何度も石牟礼さんを振り向いた美智子さま
天皇家と水俣とは、深い因縁がある。皇太子妃雅子さまの祖父は、興銀を経て1964年から71年まで、チッソの社長だった。患者や支援者たちが押し掛け、大荒れになった70年のチッソ株主総会の映像には、議長席に座る姿が映っている。この祖父の経歴が、ご結婚に至る過程で問題視された時期もあった。皇太子さまは93年の婚約発表の記者会見で、雅子さまとの話がいったん途絶えた理由として、「チッソの問題もありまして、宮内庁の方でも慎重論が出て・・・」と明かしていた。
こうした事情も熟知したうえで両陛下は水俣に向かったと思われる。公式スケジュールでは「水俣病資料館」の訪問が公表されており、そこで予定通り「語り部の会」の会長から水俣病の経緯と悲惨さを聞いた。そのあと天皇陛下は「本当にお気持ち、察するに余りあると思います」と、異例ともいえる長い感想を語った。居合わせた職員らもびっくりして聞き入ったという。この少し前に、実は両陛下は、「胎児性患者」と極秘の面会をすませていた。夕方になって、その事実が宮内庁から公表された。
石牟礼さんは、この面会には立ち会えなかった。せめてお見送りだけでもしたいと、帰京する両陛下を熊本空港の通路で待った。「美智子さまは石牟礼さんの姿を見つけて一瞬歩み寄ろうとしたが、警備の関係から近寄ることができず、何度も振り向いてお辞儀をしながら、階段を上がっていかれた」(熊本日日新聞、10月29日)
ほどなく、若い侍従が車椅子の石牟礼さんのところに近づいてきた。皇后さまからの御伝言がございますという。誰もいないところに移動してほしいと言われ、空港ロビーの奥まったとこに退くと、こう告げられた。「お見送りに来ていただいてありがとう。そして、これからも体に気をつけてお過ごしください」(『ふたり――皇后美智子と石牟礼道子』より)。
石牟礼さんは、この美智子さまとの触れ合いに象徴されるように、水俣の鎮魂を通して多くの人と心を通じ合った。高山氏は同書のあとがきで記す。「タイトルの『ふたり』というのは、何も美智子皇后と石牟礼道子の二人に限定されるものではない。それは本作を読めば、お分かりいただけることと思う」。

