現状
株価上昇で、収益が急激に回復する

東京証券取引所の現在の建物
バブル崩壊以降、日本の証券会社は業績不振に直面してきた。特に個人の株式市場離れが進み、株式の出来高が大幅に落ち込んで、証券会社の収益源である株式売買委託手数料が急減し、株式の委託売買に大きく依存する中小証券だけでなく、大手証券も急激に業績が悪化した。また、企業の資金需要が低迷し、社債などの新規発行も減って、引受業務も低迷した。会社自身が株式の売買を行う「自己売買」などでやっと利益を計上する状況が続いたが、この数年の株式市況の回復で業績も急速に回復に向かっている。
2003年度の業績を見ると、野村ホールディングスの経常利益が前期比で約6倍も増えるなど、各社とも急速に業績を回復している。10年以上に及ぶ業界の統合・合理化も、ようやくその成果を発揮するようになってきている。
会社の数は増えたが従業者は激減
証券会社の数は、90年の272社をピークに減少傾向が続いてきたが、93年以降は増加傾向を示し、97年には291社となっている。現在では280社台で推移している。90年代に一貫して深刻な証券不況が続いてきた割には、証券会社の数が減らず、むしろ80年代後半のバブルの頃に比べると数は増えている。これは金融ビッグバンによって、新規参入が容易になり、外資や異業種からの新規参入が増えたことによるものだ。
このように証券会社の数は増えたが、営業所と従業者(役員と職員の合計数字)は、大きく減少している。
営業所の数は91年の3296をピークに減少し続け、2002年末には1604となっている。従業者の数も90年の16万1695人をピークに減少を続け、2002年末には9万1266人となっている。証券会社の数は増えているのに営業所や従業者の数が激減しているのは、投資家の株式離れに加えて株式委託手数料の値下げ競争が激化し、証券会社の収益が悪化して、多くの営業所や従業者を維持することができなくなったためだ。また最近では、個人投資家の取引の約8割近くをネット取引が占めるといわれており、こうしたネット取引の普及が、営業所や営業マンの数の減少に拍車をかけている。
中堅証券を襲った再編の嵐
大手証券ほどに収益が多様化しておらず、中小企業のように身軽に変身ができない準大手証券、中堅証券は自力で生き残るのが難しく、再編の道を選ぶしかなかった。
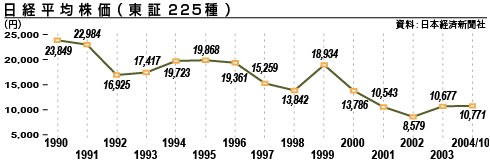
証券会社は大別して、大手証券系、大手銀行系、独立系に分けられる。もっぱら業界再編の中心となったのは、大手銀行系の証券会社だった。
90年代の不良債権の処理の過程で、大手銀行そのものが再編によって4つのグループに集約されたのをきっかけに、大手銀行ごとに傘下に連なっていた系列の証券会社もまた再編の対象となったのである。
銀行系の証券会社は、めまぐるしい合併を繰り返したので、かなり日本の証券業界に精通した人間でも、現在の社名と昔の社名を結びつけるのは骨の折れる作業となっている。
まず2000年4月に新日本証券と和光証券が合併して新光証券(みずほ銀行系)が誕生した。2002年6月には、つばさ証券(ユニバーサル証券、第一証券、太平洋証券、東和証券の4社が2000年4月に合併してできた証券会社)とUFJ キャピタルマーケッツ証券(三和証券と東海インターナショナル証券が2001年7月に合併してできた証券会社)が合併してUFJ つばさ証券(UFJ銀行系)が誕生した。
2002年9月には、国際証券、東京三菱証券、東京三菱パーソナル証券、一成証券の4社が合併して三菱証券(東京三菱銀行系)となり、2003年4月には、さくらフレンド証券(山種証券と神栄石野証券が2000年4月に合併してできた証券会社)と明光ナショナル証券(明光証券とナショナル証券が1999年4月に合併してできた証券会社)が合併し、SMBCフレンド証券(三井住友銀行系)が誕生している。
旧・日本勧業角丸証券は1990年10月に勧角証券に社名変更した後、2000年10月には、親銀行の合併にあわせてさらに社名を変更し、みずほインベスターズ証券となっている。バブル期と同じ社名で存続している準大手証券会社は、岡三証券くらいである。
持ち株会社へ移行した大手証券
大手証券も組織改革によって持ち株会社を作り、その下に従来のリーテイル部門(個人向け営業)、ホールセール部門(法人向け営業)などを分社化して、1つのグループを形成しているために、かえって実態が分かりにくくなっている。
たとえば野村グループでは、持ち株会社である野村ホールディングスの下に、野村證券(個人向けと法人向け)、野村年金サポート&サービス株式会社、野村アセットマネジメントなどの子会社がぶら下がる形でグループを形成している。また野村総合研究所は野村証券グループの関連会社だが、別途のグループを形成している。
大和グループでも、持ち株会社の大和証券グループ本社の下に、大和証券(個人向け)、大和証券SMBC(法人向け)、大和証券投資信託委託、大和総研、大和住銀投信投資顧問などの子会社がぶら下がり、グループを形成している。
日興グループでも、持ち株会社の日興コーディアルグループの下に、日興コーディアル証券(個人向けと法人向け)、日興ビーンズ証券(個人向け)、日興シティグループ証券(法人向け)、日興アセットマネジメントなどの子会社がぶら下がり、グループを形成している。
大手証券といえば、かつては野村證券、日興証券、大和証券などのことを指していたが、今では、野村ホールディングス、大和証券グループ本社、日興コーディアルグループなど大手証券の持ち株会社のことを呼ぶようになっている。
銀行が野村を包囲する構図
すでに証券業界は、ほとんどがみずほ、東京三菱、三井住友といった四大メガバンクに実質的な経営権を握られている。そしてこの銀行系の証券会社が、銀行とは一線を画した独立系の野村グループを包囲する構図ができあがっている。
銀行は約10年前に証券子会社を相次いで設立し、債券の売買業務や引き受け業務に進出した。だが販売網の拡大に予想外に苦戦した結果、親密な準大手以下の証券各社を子会社化していった。それでも個人の資金の取り込みは、銀行系証券を含めて思うように進んでいないのが現状だ。
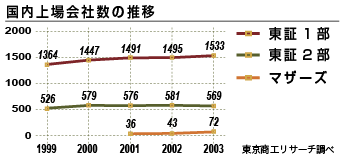
一方、大法人向けに特化した外国系証券会社の台頭などもあって、法人向け事業の受注獲得競争は激化の一途をたどっている。受注の単価が低下するなどの影響で、大法人部門は従来のように収益を上げにくくなっている。
その中で、企業再生をスローガンに各社が力を注いでいるのが、中堅規模以下の法人を対象としたインベストメントバンク(投資銀行)業務だ。経営不振の法人やベンチャー企業への支援や不動産再開発のスキームを提案・実行して手数料を稼いだり、専門のファンドを通じて資本を投入し、そして支援先企業の価値を高めた後に他へ売却する方法などをとっている。
米投資銀行の大手、ゴールドマン・サックスと三井住友フィナンシャルグループ、米証券大手のメリルリンチとUFJホールディングスが、それぞれ資本参加を含めた提携を行ったのは、日本側が投資銀行業務のノウハウを現場に導入したいという狙いもある。
一方、この投資銀行業務分野では、覇権を狙う野村は独立系としての強みを活かし、地方銀行への投資信託などの商品提供や公募増資引き受けなどで結びつきを強めようとしている。
歴史
銀行に比べ地位が低い証券市場

東京証券取引所の旧建物(1931年から1982年まで使用)
日本の証券業界は長い間、金融界の中で奇妙な立場に置かれてきた。日本の戦後の経済復興は銀行を経由した「間接金融」を柱に行なわれてきた。政府は低金利政策によって預金金利を低く抑え、集められた低利資金は銀行を通じて産業に貸し出された。こうした政府の金利規制という政策は、価格メカニズムに価格決定を委ねる市場経済には馴染まない。株式市場や債券市場は、基本的に需給と投資家の思惑によって価格が決定される。本来なら市場機能を活用することが、経済効率が一番よく、資源配分にとっても好ましいといえるが、戦後の日本の資金不足の状況を考えると、限られた資金を産業に集中的に、しかも低いコストで提供するという、一種の資金割り当て政策は、株式市場や資本市場を通す「直接金融」よりも有効であったといえる。
企業は長期の設備投資資金などを調達するために増資をしたり、社債を発行したりするのが通常の形である。だが、日本の金融システムでは、長期資金の提供は銀行、特に長期信用銀行や信託銀行を通して行なわれた。あるいは、商業銀行が短期の貸し出しをロール・オーバー(決済繰り延べ)して実質的に長期資金の供給を行なってきた。そうしたシステムのもとでは、株式市場や債券市場は、周辺部分に位置する、つまり補完的な金融市場でしかなかった。そのことは、戦後の日本の証券会社の特徴を決定することになった。
個人資産に占める株式の比率は低い
長い間、日本では、資産運用のための最大の資産は銀行預金であり、株式や投資信託ではなかった。個人の株式保有は極めて低水準に留まっていた。何度かあった株式ブームの時に、一時的に個人の株式保有額が増えることはあったが、決して資産運用の主流になることはなかった。証券会社は“株式の大衆化”運動を行い、個人投資家を増やす努力を行なったが、なかなか成果が上がらなかった。株式投資は投機であるという根強い意識が、個人投資家のなかにあった。
また、株式市場の寡占化による弊害が、個人投資家を株式投資から遠ざけている面もあった。戦後の証券業界では、4社寡占体制が成立していた。4社とは、野村證券、大和證券、日興證券、山一證券であり、株式市場での取り扱いだけでなく、株式や社債の引受業務でも、4社はほぼ市場を独占していた。また、株価形成に対する4社の影響力は強く、時には株価操作的な動きもあるなど、株式市場の民主化は大きく遅れていた。投資信託も証券会社によって実質的にコントロールされるなど、個人投資家にとって株式投資は必ずしも優良な投資商品とはいえなかった。
証券の売買手数料が自由化される
80年代に入って進んだ金融自由化が、証券業界を活性化させる役割を果たした。まず、財政赤字が拡大するとともに、政府は金利を規制し続けることができなくなった。国債発行市場では政府が規制によって、高い価格(=表面利率が低い、低クーポン)で金融機関に売りつける一方で、金利の自由化が先行した流通市場では国債価格が政府の大量発行によって、暴落(=金利が上昇)した。
金融機関が資金繰りの必要性から、発行市場で無理矢理買わされた国債を流通市場で売ろうとすれば、売却損が出るため、発行市場での高い価格での国債引き受け(購入)を渋り始めた。国債の発行量が少ない時代は、金融機関は満期まで抱え込んでいたので、こうした問題は生じなかった。
こうした金融機関の買い渋りによって、発行市場における低クーポンの発行が困難になり、発行市場でも金利の自由化が進んだ。その結果、中期国債ファンドのような自由金利の商品ができて、それが預金金利の自由化を促す触媒になった。
資本市場での発行の自由化は、金利自由化と歩調をあわせて起きた。また、投資家として成熟してきた個人も、低金利や低リターンに甘んじることなく、より高い投資リターンを求めるようになってきた。そこで問題となったのは、証券の売買手数料が高いことである。欧米では70年代から委託売買手数料の自由化が進んでおり、日本でも“日本型ビッグバン”によって証券の売買手数料の自由化が行なわれた。委託売買手数料の自由化は、証券会社の経営環境を大きく変えた。
崩れる証券業界の寡占体制
こうした自由化の進展と歩調をあわせるように、4社寡占体制も足元から崩れ始める。80年代に証券業界はバブルによる株価ブームを満喫する。好況を背景に証券各社は、コンピュータなどに過剰なシステム投資を行なう。だが90年代初めにバブルは弾け、株価は急落、株式の出来高は急激に落ち込む。過剰投資となった証券会社は、経営に行き詰る。
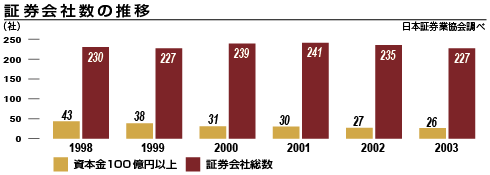
97年に4社寡占体制の一角を占めていた山一證券が自主廃業し、事実上倒産した。同社の場合、投資家の損失を補填する“飛ばし”によって膨大な損失が発生し、それを隠蔽していたことが命取りになる。また、過剰な設備投資をした準大手の三陽証券も、97年に経営が破綻した。かつて山一證券は1965年に同様な経営危機に直面したことがあるが、そのときは日本銀行の特別融資で生き延びた。しかし、80年代の金融自由化という新しい状況のもとでは、もはや従来型の救済は不可能で、最大手証券会社の1つであった山一證券は倒産する以外に道はなかった。
認可制から届出制への変更が新規参入を促進
4社寡占体制は山一證券の破綻で崩れるが、同時に証券業界への新規参入促進も業界地図を大きく変えることになる。89年に、証券会社の設立は「免許制」から「届出制」に変わり、他産業からの参入が容易となった。新規参入企業との競争から守られ、既得権を満喫できた証券業界は、これを機に、抜本的な経営の見直しを迫られることになる。

多くの株式仲買人と東京証券取引所の旧立会場
異業種からの参入としては、ソニーがマネックス証券に出資したり、インターネット企業の楽天がDLJディレクト証券(2004年7月に社名を楽天証券に改称)を買収したり、ソフトバンクがソフトバンクフロンティア証券(2004年にワールド日栄証券と合併してワールド日栄フロンティア証券になる)を設立したりしている。こうした新規参入証券の特徴は、多くがネット証券である。従来の、店舗を設置し、大量のセールスマンを投入する営業形態は収益性が低い。低い手数料を武器に、ネット取引を拡大することで、独自の営業基盤を確立している。ネット証券の最大手は松井証券で、ネット証券会社の出来高に占めるシェアは急速に高まってきている。
証券会社も、3社が持ち株会社を設立
さらに、それまで証券業務兼営を禁止されていた銀行が、持ち株会社を設立して、そこから証券子会社を設立し始めた。こうした形で、銀行の証券業務への進出が認められたことも、証券業界を大きく変えることになった。特に銀行系証券会社は企業と密接な関係にあり、株式発行や社債発行で証券会社よりも優位な立場に立つことができる。さらに、大衆投資商品である投資信託も銀行の窓口で販売できるようになり、従来から存在する証券会社の収益源を奪うことになった。銀行系の証券会社としては、三菱証券、UFJつばさ証券、みずほインベスター証券がある。
一方、従来の証券会社も、新規参入証券会社との競争に対応するために持ち株会社を設立している。現在、証券会社系の持株会社は野村ホールディングス、大和證券グループ、日興コーィアルグループの3社で、それぞれ異なった戦略を取っているのが注目される。野村グループは独立路線であるのに対して、大和證券グループは三井住友銀行と提携関係を強めており、日興コーディアルグループは国際資本であるシティグループとの提携によって生き残りを図っている。
将来を展望するための3つのポイント
ポイント1
投資銀行業務の拡充できるか
証券業界は「自由化」と「国際化」という大きな動向に対応し、生き残りのための経営戦略を模索している。大手証券は金融業界の自由化を受けて、銀行同様に持ち株会社を設立し、従来のリテール(個人向け)分野の強化を進める一方で、投資銀行業務の強化を進めている。アメリカでは委託売買手数料の自由化が行なわれたあと、証券会社は投資銀行業務に力を入れたり、リテール業務に特化したり、調査機能の充実を図るなど様々な対策を講じたが、日本の証券会社も同様な対応策を取っている。まず、リテール部門では、従来の営業社員による販売に加え、ネット取引部門の強化を行う一方、投資信託業務の拡充、投資家から売買を一任された「一任勘定」による顧客資産の運用の拡大などに取り組んだ。
リテール部門の強化に加え、投資銀行業務の拡充が大手証券会社にとって急務となっている。この分野では、日本の証券会社は欧米の投資銀行に大きく後れを取っている。特にデリバティブ商品の開発能力やM&A(企業の合併と買収)分野ではノウハウの蓄積は十分ではない。大手証券会社が総合証券として国際市場をリードし、国際的な地位を確立するには、投資銀行部門の強化は不可欠である。
ポイント2
中小証券会社は生き残れるのか

東京証券取引所のマーケットセンター
他方、中小証券会社は、大手証券とは違った戦略を取っている。それは、特定の分野へ集中することである。ネット証券会社は、徹底的な人員削減を行い、顧客の投資家に投資情報や様々な投資ツールの提供を通して、営業基盤の確保を目指している。長期的には営業社員を通しての株式の売買から、ネット証券を通した売買が主流になることは間違いない。また、ネット証券以外では、自己売買機能を強化したり、中国株など特定の商品に特化したりして生き残ろうとする中小証券会社も存在する。
ポイント3
銀行系の証券会社はどこまで伸びるか
もう1つ大きな流れは、銀行系の証券会社の参入である。前述のように銀行は証券子会社を設立して証券業務に参入しているが、同時に既存の証券会社を買収して銀行の傘下に収めることで、急速に証券業務のノウハウを獲得しつつある。銀行系の証券会社は、親会社が銀行のため、企業顧客へのアクセスが容易であり、株式や社債の発行引き受け業務で優位性を持つほか、将来は銀行窓口を通して株式の売買が可能になることから、大きな成長可能性を秘めた存在といえよう。既に銀行窓口での投信販売は行なわれており、消費者の銀行に対する信頼感を武器に、着実に販売シェアを増やしている。株式売買に関しても同様なことが起こると十分に予想される。