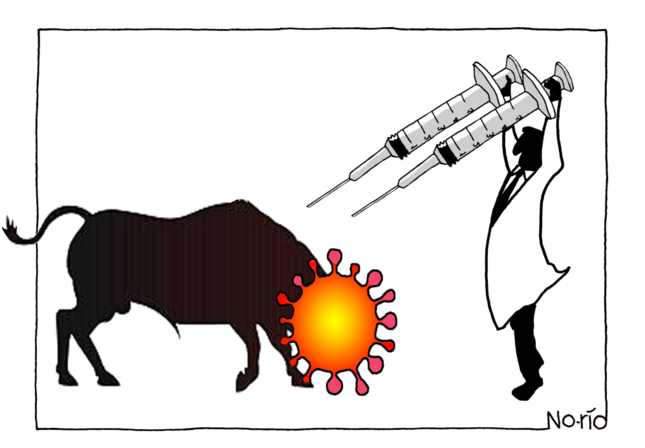スペインでは昨春のコロナ第1波の後、いったん小康状態になったが、昨秋に突入した第2波が長引き、厳しいロックダウンが続いている。繰り返し襲来するコロナ禍に、人々はどう耐えているのか。スペイン・バルセロナで10年にわたって豆腐店を経営してきた清水建宇(たてお)さん(73)と考える。
取材で訪れたバルセロナが気に入る
清水さんと言えば、2000年から03年にかけ、テレビ朝日の「ニュース・ステーション」のコメンテーターとしてご記憶の方も多いだろう。といっても、スタジオでコメントするだけでなく、事件・事故の現場から、久米宏キャスターに報告する「現場派」記者の姿勢を貫いたジャーナリストだ。
清水さんは北海道札幌生まれ。道警勤務の父親に連れられて道内を転々として育ち、道立札幌南高から神戸大経営学部に進み、1971年に朝日新聞に入社した。佐賀、下関支局から九州にある西部本社・社会部に移り、東京社会部で警視庁キャップを務めるなど、事件記者として鳴らした。その後、出版局、編集委員などを経て、テレビ出演もしながら、毎年出版局刊行の「大学ランキング」編集長を務め、教育事情にも精通している。
その人がなぜ、バルセロナで豆腐店を?そう疑問を持たれる方も多いだろう。私自身、その鮮やかな転身振りに、度肝を抜かれた。
実は私は清水さんの高校の後輩にあたり、新聞社でも同じ「飯場」の後輩だった。
「飯場」というのは新聞社の業界用語で、連載企画の取材班を指す。全ての取材チームが「飯場」になるわけではなく、ある「親方」格のキャップのもとに参集し、解散後も長くつきあう疑似血縁型の「一家」や「組」に近い。「同じ釜の飯を食った仲」という意味での「飯場」であり、そのつながりは所属する部を超えて、濃密だ。
私の場合、編集委員の疋田桂一郎さんがキャップになり、80年代前半に、朝日新聞日曜版で2年半にわたって連載した「世界名画の旅」が、その飯場だった。当時私は学芸部に所属していたが、「疋田飯場」では、社会部の清水さんや、その後「天声人語」を担当する高橋郁男さんらに鍛えていただいた。つまり清水さんは、疋田さんを師匠とする私にとっての「兄弟子」なのである。
実は07年に清水さんが定年で退社する前、何度か私は、清水さんから「将来はバルセロナで豆腐屋になる」という話を聞かされていた。スペイン語を学び、その準備をしていらっしゃるという話も聞いた。だが、まさかその夢を実現するとは想像しなかった。バルセロナに住む。それはあり得る。日本で豆腐屋に挑戦する。これも、手打ちソバの趣味が高じて蕎麦屋を開く路線の延長線上に想像力を膨らませれば、理解できる。だが「バルセロナで豆腐屋」となれば、話は別だ。なにしろ、清水さんにとって、バルセロナに住むのも、豆腐店を経営するのも、初めての経験なのだ。
昨年に出た雑誌「熱風GHIBLI スタジオジブリの好奇心」6月号に寄せた文章で、清水さんは、「事件記者」からの転身について、次のように書いている。
ある日、日曜版「世界名画の旅」取材班に移るよう命じられ、柄にもなく画集を眺め、美術書を読み、海外へ長期出張することになった。1年半の間に訪れたのはパリやニューヨークなど15カ国の21都市。そのなかでいちばん心に残ったのがバルセロナだった。気候がよく、食べ物が安くておいしいだけではない。アジアから来た異邦人として奇異の目で見られなかったのは、この街だけだった。ピカソ、ダリ、ミロ、ガウディらを育んだ自由の気風が気に入った。
定年後の第2の人生をバルセロナで過ごしたい。その思いはふくらむばかりだったが、問題は私が大好きな豆腐、油揚げ、納豆などが手に入らないことだ。ならばバルセロナで自分が豆腐屋になるしかない。退職するや近所の豆腐屋さんに弟子入りし、必要な機械を中古で買い集め、バルセロナの中心部に店を借りて開業した。それから10年になる。
職業柄、記者はファクトをもとにストーリーにするのが得手だ。だが清水さんら先輩からは、「出来過ぎた話は疑え」と教えられてきた。2021年2月3日、バルセロナ在住の清水さんへのZOOMインタビューは、この質問から始まった。
「一身二生」で豆腐屋になる夢を実現
久しぶりにお目にかかる清水さんは10年前と変わりなくお元気で、精力的だった。私の質問に対し、「あそこに書いた通り」と軽くいなした後、こう付け加えた。
「実は、定年が近づいて、第2の人生をどう生きるかを考え、頭に浮かんだのは伊能忠敬の『一身二生』の生き方だった。バルセロナは気に入ったし、いつか豆腐屋もやりたいと憧れていた。でも、住んだことのないバルセロナで、やったことのない豆腐屋を仕事にするなら、これは自分にとっての『一身二生』になるのでは、と思った。みんなに『バルセロナで豆腐屋になる』と公言したのは、自分の退路を断つためだった」
「一身にして二生を経る」とは、幕藩・明治の二つの時代を生きた福沢諭吉が使って広まった言葉だ。しかし、隠居してから弟子入りして暦学や測量を学び、全国を測量した伊能忠敬の人生ほど、この言葉に似つかわしい生き方はないだろう。
多くの人は定年後、それまでの生き方から自由になり、自ら封じてきた夢を追ってみたいと思う。しかし多くは、それまでの重力圏から逃れられず、かつての「実績」や「肩書」にとらわれ、組織にしがみつこうとする。清水さんがそうならなかったのは、持ち前の行動力と集中力、それにご家族の支えがあったからだろう。
バルセロナはイベリア半島北東部、地中海に臨むカタルーニャ州の港町だ。スペイン第二位の人口160万人を抱える。イスラム支配の後、10世紀にフランク王国から独立してカタルーニャ君主国になり、一時は隆盛を極めた。だが、スペイン統一後にカスティーリャ王国の中心地はマドリッドに移り、次第に周縁化されていく。
もともとカタルーニャは独自の言語・文化・歴史をもち、マドリッドへの対抗意識が強い。地中海に面したフランスなど他地域とのつながりも深い。繊維業も盛んで、その富をバックに20世紀初頭には多くの芸術家が輩出した。
1936年~39年のスペイン内戦では、共和国を守る左派の統一戦線側に立って、反乱を起こした右派のフランコ軍と戦い、敗れた。ちなみにこの内戦では、共和国派に投入された国際旅団の一員としてヘミングウエイが「誰がために鐘は鳴る」を書き、オーウェルは「カタロニア賛歌」を書いた。また共和国派のピカソは、カタルーニャと共に共和国側に立ったバスク地方が、フランコ反乱軍を支援するドイツ軍から無差別空爆された惨禍を大作「ゲルニカ」に描き、反戦平和の不朽のシンボルになった。フランコ独裁の下で、1975年にフランコが死ぬまで、カタルーニャの言語は禁止された。
こうした背景から、カタルーニャ地方はスペインからの独立意識が強く、2010年代には二度の独立住民投票を行うなど、いまだにその流れは続いている。独裁には抵抗し、抑圧に対して抗議の声を挙げ続けるバルセロナは、たしかに清水さんが書いておられるように、欧州でも最も「自由の気風」で知られる町と言っていいだろう。
リーマンショック後の不況のただ中に開店
バルセロナは、姉妹都市の神戸によく似ている、と清水さんは言う。清水さんが学生生活を送った神戸と比べると、山を背にした港町という地形も、人口もほぼ同じだ。違うのはバルセロナが世界でも名高い国際観光都市という点だ。
2019年にスペインを訪れた外国観光客約8千4百万人のうち、約2千万人がバルセロナを訪れた。日本全国での外国人客が盛期でも3千万人程度だったことを思えば、バルセロナの観光人気の程度がよくわかる。
バルセロナには、豪華クルーズ客船が12隻同時に横付けできる専用埠頭があり、客は世界中から空路でやってきて、バルセロナ観光を楽しんでから地中海クルーズを楽しむ。
エル・プラット国際空港は2つのターミナルがあり、中国や中東からの直行便のほか、欧州各地の路線と結ばれている。19年の乗降客は5300万人だった。
清水さんはスペイン語を学び、日本の豆腐店で一から修行を重ねたうえで2010年、豆腐の製造機械や冷蔵ショーケースなどの冷機を持ち込み、2010年4月に「TOFU CATALAN」を開業した。
2010年のスペインといえば、08年のリーマンショックに始まる欧州債務危機に、不動産バブル崩壊のダブルパンチが加わり、不況にあえぐ真っ最中だった。
スペインでは小さな金融機関が乱立し、しかも政治家がからんだ不動産を高値で買ったり貸し込んだりしていたため、たちまち経営危機に追い込まれた。スペイン政府はEUと欧州中央銀行に頼み込んで1000億ユーロ(約10兆円)の銀行救済資金を出してもらったが、それと引き替えに超緊縮財政を約束させられた。
消費税率を21%に引き上げる、公務員の賃金をカットする、大学や学校、医療の予算を削り、人員も減らす。高齢者福祉への補助も減らす。これはやがてコロナによる「医療崩壊」や「介護崩壊」の遠因ともなったのだが、それはまた、後で触れよう。
ともかく、そんな逆風の中に船出をした清水さんだが、幸か不幸か、不況は「追い風」になった面もあるという。
私も現地取材で見聞きしたが、たぶんスペインはイタリアと並んで、一日に数多く食事をする国だろう。清水さんはそれを、「スペイン人の一日は、バルに始まってバルに終わる」と表現する。
バルは喫茶店と居酒屋を一つにしたような店だ。朝、バルでクロワッサンとミルクコーヒーの朝食を取り、午前11時にまたバルで小皿料理をつまむ。午後1時からレストランやバルで昼食を取り、夕方、またバルで何かをつまむ。晩ご飯は午後9時ごろ、というのが一般的な食生活だ。5回とも外食という人も少なくなかった、という。
スペインの昼休みはふつう2時間。その間に自宅に帰るかレストランで食事をとるのが当たり前だった。だが清水さんが開店したころ、不況に見舞われたスペインでは最高裁が、労働者の同意がなくても、雇い主が勤務時間を変更できる、という判決を出し、長年の慣行に改革の道を開いた。
清水さんの店は三本柱を基本にした。第一は、伝統的な豆腐、油揚げ、納豆の販売。第二は日本食品、食材の販売。そして第三が「弁当」だった。それまで、自宅かレストランでゆっくり昼食を楽しんでいたスペイン人が、昼休みを削られ、弁当を買って食べるようになっていたのだった。
「もともと、うちの豆腐屋は、非営利法人NPOのようなもの。低空飛行で続けばいいと考えていた。従業員を減らし、三本柱を据えたことで、浮き沈みなく経営を続けてこられたと思う」
バルセロナを襲ったコロナ第1波
だが清水さんが長年親しんだバルセロナは、昨年3月15日、スペイン政府が「警戒事態」を宣言してから、一変することになった。
外国からの観光客が一夜にして入国できなくなり、クルーズ船は姿を消し、空港は一部のローカル路線だけになった。レストランやカフェ、バルはすべてシャッターを下ろし、サグラダ・ファミリア聖堂などの名所や美術館は入り口を閉ざした。
すべての種類の学校が閉鎖された。ホテルも閉鎖された。スペインでは街角のキオスクで新聞や雑誌を買う人が多いが、これも閉じた。開いているのは銀行や病院、水道・電気・ガス、ゴミ回収などにかかわる会社、食品や生活必需品を扱う店だけになった。地下鉄やバスは大幅に減便になり、通勤・通学の乗客がいないので、ガラガラのままだ。
だが、その日が来るまで,兆候は目立たず、コロナ禍は忍び足でやってきた。
スペインで感染が初めて確認されたのは昨年2月25日だ。バルセロナ在住の女性一人が大学病院に隔離された。バレンシア州と首都のマドリードでも感染者が見つかった。三人ともコロナが爆発的に広がっていたイタリア北部を旅行した人たちだ。
初めは感染者の接触者を調べてクラスターを追跡する手法が採られた。
しかし、初の感染者が見つかる1週間前の2月19日、イタリア北部ミラノでサッカーの国際試合があり、バレンシア州の住民2000人が地元チームを応援するために出かけていたことが判明した。一人ずつ接触者を追跡することは、もうできない。
3月5日、マドリードの老人ホームで10人が集団感染したことが判明した。翌日もマドリードの別の高齢者施設で15人の感染者と1人の死者が出た。マドリード州政府は213の高齢者施設の閉鎖を命じた。
3月9日、感染者は全国で959人、死者は16人。感染者の半数はマドリード州が占め、北部バスク州の2都市でも急増した。カタルーニャ州内の感染者は101人にとどまっていたが、その4分の1は医療従事者だった。病院が感染源になり、しかも感染した医師や看護師らが治療や隔離のために働けなくなるという二重のリスクが明らかになった。
3月13日、全国の感染者は3900人となったが、カタルーニャ州では一気に316人に倍増した。トーラ州知事は危機感を強めて「全域に非常事態を宣言する」と告示し、翌日の14日から厳しい外出規制を行うと発表した。中央政府のサンチェス首相も後を追うように「警戒事態」を宣言した。
これが、清水さんに教えていただいた「激変」に至るまでの道のりの簡単な素描だ。
医療・福祉の削減が「崩壊」への序曲
すでに見たように、債務危機と不動産バブルの直撃を受けて、スぺイン政府は大幅な公費削減を進めていた。もともと体力が弱っていた医療・福祉の現場をコロナ禍が直撃した。
スペインでは小さな商店や事業所で働く場合も、雇用主と従業員が必ず労働契約を結ぶ。この契約には職種と1ヶ月の給与額が明記され、それによって健康保険、労働保険、年金という3つの社会保険料も決まる。
社会保険の加入者は公立病院での医療費が無料となるので、庶民はみんな公立病院へ行く。救急医療や公衆衛生の引き受け手も公立病院だ。まさに国民の命と健康を守るその砦が、この10年ほど、人員と予算の削減で縮小を続けた。
清水さんは、スペイン在住のジャーナリスト、宮下洋一さんの以下の報告を引用する。
スペインは10年間で76億ユーロ(約9000億円)の医療費を削減し、首都マドリードでは約2000床のベッドが消え、3300人の医療従事者が職を失った。人口あたりの医師、看護師らの数は、英国、フランス、ドイツの半分にすぎない。せっかく公費でつくった病院もすぐ民間に売り飛ばされた。
コロナ禍の前から、公立病院の惨状は誰の目にも明らかだった。診察してもらおうと思えば3時間、4時間待ちは覚悟せねばならない。救急患者でさえ放っておかれる。清水さんの奥さんは一昨年夏、右脚を痛めて歩けなくなり、昼過ぎに救急病棟に入った。清水さんが豆腐店を閉めて午後9時に見舞いに行ったところ、まだ廊下のベッドに寝かされ、診察も受けていなかった。医師も看護師も必死に仕事をしているが、数が少なすぎるのだ。
一昨年暮れには、バルセロナで毎週のように、医師と看護師らがデモをして「人員を増やせ」「備品を充当せよ」「救急手当てを上げよ」と叫んだ。医療の現場はすでに、限界に近かったのである。
コロナ禍は、揺らぐ天秤の片方の皿に、重い荷を載せた。
マスクも防護服も人工呼吸器も足りない。集中治療室もわずかしかない。病院は大混乱に陥った。看護師らはゴミ用のポリ袋を絆創膏で貼り合わせた急ごしらえの防護ガウンを着て仕事をした。感染するのも当然だ。
昨夏までスペインでは、約20万人の感染者のうち医療従事者が3万5000人に上った。ほぼ6人に1人の割合だ。医療従事者は、症状が治まったり隔離が終わったりすると、すぐに病院に戻り、仕事を続けた。その様子は新聞やテレビで報じられた。
欧州で最も厳しい外出禁止令
清水さんによると、昨年3月15日から実施された外出禁止令は、欧州でも最も厳しい措置だった。
外出が許されるのは、食料品や生活必需品の買い物、病院への通院、お年寄りや障がい者の介護、銀行での引き出しなどだ。
犬の散歩は良いが、人間だけの散歩、ベンチでの休憩、葬式や結婚式も許されない。
すべての市民は、氏名と住所、納税者番号、外出理由を書いた書類を携行しなければならない。警察官があちこちで検問し、この外出理由の書類通りかどうか、目を光らせた。
違反すれば100ユーロ(約1万2000円)から6万ユーロ(約720万円)の罰金、悪質な場合は1年間の禁固刑が課される。欧州で最も厳しい罰則だ。
気候が良くなり、自宅に籠もるのが辛い季節だったせいもあるだろうが、規則を破って外出する人が続出した。罰金を科せられた人は全国で25万人にのぼったという。
しかし、新聞やテレビを見ても同情する声はなかった。規則を緩めるべきだという提言も見かけなかった。ほとんどの市民は黙って耐えた。店も事業所も閉店の指示に従った。
厳しい外出禁止令が守られたのは、おそらく2つの理由からだろうと清水さんは言う。
一つは感染者と死者が恐ろしい勢いで増え続けたことだ。外出禁止令が出た時点で感染者は全国の累計6900人余だったが、1週間後には2万7000人と4倍になった。2週目はさらに増え方が激しくなり、3月30日には一日の新規感染者が9200人にのぼった。「明日は我が身か」と切迫した恐怖感にかられた人が多かっただろうという。
加えて、家族の絆の強さが際立った。3月末の死者の総数8189人のうち、9割は70歳以上の高齢者。若者や働き盛りの世代代の死亡率は極端に低かった。
だがスペインでは家族の結びつきが強く、クリスマスイブには祖父母を訪ねて一緒に郷土料理を味わう習慣が根強い。イブは商売にならないからと閉店するレストランがかなりあるほどだ。若い人々も他人事と考えず、「じいちゃんやばあちゃんが危ない」と受け止める。危機感は世代を超えて共有された。
二つ目の理由は、十分ではないにせよ経済的な救済策が決まったことだろうと清水さんは指摘する。
外出禁止令から8日目、75%以上収入が減った自営業者に対し、それまでの収入の70%を国が補償するという発表があった。中小企業が従業員への給与支払いのために銀行から借り入れる場合、その80%を国が保証することも決まった。企業に対してはコロナ禍を理由にした解雇を禁止した。小規模業者や個人の家賃は支払いの猶予が認められ、家主が借りた人を追い出すことを禁止した。電気、ガス、水道代の支払い猶予も認められた。
スペインでは集合住宅の管理組合に雇われて掃除の仕事をする女性が大勢いる。いくつかの集合住宅を掛け持ちし、雇用契約がはっきりせず、労働保険に入っていない人も多い。こうした弱い立場の人も、それまでの収入の70%が国から支払われることになった。
救済策には細かな条件がついていて、申請の手続きは簡単ではない。しかし、スペインには行政書士、会計士、税理士、社会保険労務士を兼ねたような「ヘストール」と呼ばれる職業があり、小さな商店や事業所も例外なく契約している。清水さんの豆腐屋も契約していた。このヘストールが救済策の申請を代行してくれるので、商店主や事業主は書類と格闘しなくても済む。厳しい外出禁止令のもとで平静がどうにか保たれたのは、こうした仕組みに負うところもあっただろう、と清水さんはいう。
感染しない、させない
前にも触れたように、スペイン人とバル文化は、切っても切れない。外出禁止令と共に、バルやレストランが閉鎖された衝撃を、普通の日本人が想像するのは難しいかもしれない、と清水さんがいう。
もちろん、食事は自宅でつくるしかない。材料は買ってくるしかない。
バルセロナにはショッピングセンターはほとんどなく、ワンフロアの小さなスーパーがあちこちにあるだけだ。どの店も客の数を制限したので、入りきれない客が路上で行列をなした。しかも2メートル間隔で並ぶので、長い行列になる。やっとの思いで店内に入ると、係員から両手に消毒液をかけられ、使い捨てのポリ手袋を渡される。商品を手で直接触らせないためだ、このルールはどのスーパーでも厳格に守られた。手袋が底を突いた店は代わりにポリ袋を配り、客はみんなポリ袋を手にはめて買い物をした。
清水さんの店も入店は2人までに制限し、入り口に消毒スプレーと使い捨ての手袋を置いた。店では味噌や醤油、うどんや蕎麦、ラーメンなどの日本食材を置いている。行列ができてもよさそうなものだが、外出禁止令が出て、客は3分の1に激減した。
「食品の買い物は自宅から500メートル以内で」という規則があったためだ。店から見ると半径500メートル以内の人しか来てもらえない。
ある日清水さんは、常連客から「豆腐を買いたいが、自宅から遠いので行けない」という電話を受けた。「500メートル以内かどうか、だれにも分からないでしょう」と返すと、「検問の警察官は外出理由書の住所を見て、500メートル以上離れているから、戻りなさいと言うんです」との返事だった。
規則は単なるお題目ではないと痛感したという。警察官の感染者も当時、2000人にのぼった。取り締まりる方も、危険を覚悟の上で検問しているのだった。
突貫工事の医療体制強化
スペインの第1波への対応で注目すべきなのは、厳しいロックダウンを敷く一方、初期の段階で、崩壊しかけていた医療を立て直す施策も急ピッチで進めたことだ、と清水さんはいう。
外出禁止令から4日目、マドリードでは体育館やホールなどを病院に改造する工事が始まり、国際会議場は1400のベッドと96の集中治療室を持つ巨大な仮設病院になった。
ホテルの広い駐車場に軍のテントがいくつも張られ、野戦病院がつくられた。どれも軍の工兵隊や消防署員らを動員する突貫工事で、工事開始かから数日後には最初の患者が入院した。閉鎖中のホテルも借り上げられ、軽症者の収容施設になった。
死者が急増し、公営墓地で埋葬しきれないため、マドリード市はスケートリンクを臨時の遺体安置所にした。1800の柩を並べられるスペースが確保された。
バルセロナでも4つの公立病院の近くにある体育館を仮設病院にする工事が始まった。医師や看護師らが通いやすく、患者の移送もしやすい。合計で1000以上の病床があり、ここに軽症者を入院させて、病院本体は重症患者の治療に取り組めるようにした。
感染検査の能力も大幅に引き上げた。北部のガリシア州では韓国にならってドライブイン方式の検査所もできた。
3月30日にはスペインの軍用輸送機が中国へ飛び、マスク、防護ガウン、人工呼吸器、ウィルスの検査機器などを満載して戻ってきた。これらの医療資材はただちに公立病院や仮設の臨時病院に配られた。
警戒宣言に伴う外出禁止は15日間を一区切りとし、国会の承認を得て延長されるが、医療の立て直しは第一期の15日間で基礎作りをあらかた終えたと言っていい。そう清水さんはいう。
その効果は4月中旬から数字に表れ始めた。全国の新規感染者数、死者数は最悪期の半分ほどに減った。米国のジョンズ・ホプキンス大学の集計によると、スペインの「回復者(退院者)」の数がどんどん増え、4月末には10万人を超えてドイツと肩を並べるようになった。イタリアの8万人、フランスの5万人と比べてもはるかに多かった。
マドリードの国際会議場を改装した巨大な仮設病院は4月下旬、不要になったとして閉鎖されることが決まった。医師や看護師たちが大喜びして踊る映像がテレビに流れた。そのニュースは、新型ウイルスの蔓延を食い止めることができるかもしれないという期待を多くの視聴者に抱かせただろう。功労者は、貧弱な装備と設備のせいで大勢が感染しながらも医療の最前線に立ち続けた医師や看護師、検査技師らの医療従事者だった。
外出禁止令が出てまもなく、バルセロナで、そしてスペインの多くの街で、午後8時になると住民が集合住宅のベランダにたち、拍手するようになった。医療従事者に「ありがとう」と声援を送るためだ。
4月25日の土曜日、住民の拍手は一段と大きかった。口笛を吹く人やフライパンをたたく人もいた。翌日から14歳未満の子供たちの外出が認められることになったからだ。
一日に一時間、自宅から1キロメートル以内。保護者の付き添いが条件で、友達と一緒に遊ぶことはできない。ブランコや滑り台も使えない。あまりにも小さな緩和措置だ。しかし、住民にとっては大きな意味を持つ。長いトンネルの先に初めて出口の明かりを見たように感じた人が多かったろう、と清水さんは振り返る。
5月2日から、14歳以上の若者や大人がジョギングや散歩することが認められた。4日からは美容院や理髪店、書店、金物屋なども営業を始めた。3分の1のスペースだけを使い、従業員はそれぞれ1人の客と応対する、レジには感染防止の仕切りを置く、などの条件付きだ。レストランやバルも持ち帰り用の料理を販売できることになった。清水さんの豆腐店にも4軒のレストランから豆腐の予約注文があった。7週間ぶりの注文だった。
再びの暗転 第2波
スペインでは6月に非常事態が解除され、レストランやバルが再開された。客席は50%まで、カウンター席は禁止という制限はあったが、多くの店が歩道にテーブルを並べ、そこで食事を提供した。スペインやフランスはもともと屋外の席の人気が高いので、利用者にとっても好都合だ。こうして外から見る限り、街はにぎわいを取り戻したかのように見えた。
だがスペインを含む欧州は、バカンス明けと共に感染者が増え始め、10月には急速に再拡大した。第2波の襲来で舞台は再び暗転した。1日の新規感染者はフランスでは3万人を超え、イギリスでは2万3000人、スペインでは1万5000人に達し、それぞれ4月のピーク時の数倍に膨れあがった。
フランス政府は10月17日に緊急事態を宣言し、パリやマルセイユなど9都市で午後9時から翌朝6時までの外出禁止令を出した。
スペインでも政府が10月12日、新規感染者が多いマドリッド州に対して非常事態を宣言し、通勤や通学などを除く都市間の移動を禁止した。レストランも午後10時以降に新たな客の受け入れを禁止した。
カタルーニャ州では、政府の非常事態宣言がないのに、州政府の決定で10月16日からレストランやバルの営業が禁止された。
10月16日からの2度目のレストラン・バル閉店命令で、街は再び静まりかえった。屋外席のための日よけは閉じられ、テーブルや椅子は積み上げられたままになった。
商店や飲食店などの休業や減収に対して政府が補償する政策は延長された。この制度があるので、反対の動きは表面化しなかった。
バルセロナレストラン協会の会長は2度目の閉店命令が出た翌日、「バルやレストランの15%はすでに廃業している。再開した店も40%は来春か夏には消える可能性がある」と警告した。数カ月後には半分がなくなるという見通しだ。廃業した店の従業員は解雇され、失業する。新しい仕事を見つけることが困難な状況で放り出される。
飲食業だけではない。観光はスペイン最大の産業であり、国内総生産の15%(約22兆円)と260万人の雇用をもたらしていた。旅行客が4分の1に激減し、ホテルの7割が閉ざされた。
スペインには自動車工場が多く、一昨年は世界9位の年間280万台を生産した。その中の日産自動車バルセロナ工場が閉鎖されることになった。
ベーシック・インカムの実施内容
コロナ禍は健康を損なうだけではない。雇用が不安定になり、低所得者の暮らしを直撃する。困窮者をどのようにして救済するか。注目されたのが「ベーシック・インカム」である。すべての国民に一律の金額を支給し、必要最低限の生活を保障する、というのが本来の意味だ。
スペイン政府は昨年6月、「ベーシック・インカム制度を実施する」と発表し、受付を始めた。全国民に一律支給するのではなく、政府が必要最低限の所得額を定め、それに届かない国民に差額を補償する仕組みだ。最低限の所得を、単身者は月額460ユーロ(約5万7500円)、5人世帯は1015ユーロ(約12万7000円)と定め、差額を支給する。政府が想定する対象者は250万人、費用は30億ユーロ(約3700億円)。企業の優遇税制を縮小し、新たなデジタル課税を導入して財源とする。一律支給でないもののベーシック・インカムと同様の所得補償制度であり、世界で初めての実施例として欧州各国や米国が注目している。
スペインは労働組合などが支持する社会労働党と、市民運動を母体にしたポデモス(スペイン語で「我々は出来る」)の連立政権だ。この所得補償制度はポデモス主導で進められたという。清水さんはこう話す。
「この制度が国民の窮乏化を食い止められるかどうか、まだ分からない。だが市民運動の成果の一つと言える。コロナ禍が収束した後の景気浮揚や支援を打ち出す日本の『Go Toキャンペーン』などより、はるかに現実的で有効な対策なのではないでしょうか」
清水さんによると、カタルーニャ州政府は現在も、外出制限などの措置を取り、14日ごとに更新している。主な項目は次の通りだ。
○通勤・通学などを除き、不要不急の郡への出入り制限
○緊急の場合を除き、午後10時~午前6時の夜間外出の原則禁止
○飲食店は午後4時半までの店内営業、持ち帰りは午後10時、デリバリーは午後11時まで。飲食店の客は30%に制限
○公共の場の会合は6人までとし、飲食は認めない
○ショッピングセンターや小売り店は客を30%に制限
○屋内外の文化活動は収容人数の50%、500人まで
○小中高校は通学を認めるが、大学はオンラインで講義
日本と比べ、きわめて細かく、具体的な指示といえるだろう。商店は平日営業を認めるが、週末は生活必需品販売や薬局、獣医師、自動車修理、ガーデニング、書店などに営業を限定するなど、業種や業態を絞って明示しているため、ルールは分かりやすい。
「警察は第1波のような厳しい取り締まりはしていない。今回は行政ペナルティはあっても罰則はなく、その意味では第1波よりも緩やかだ。それでも、人々は黙々と指示に従い、大きな抗議やデモは起きていない」
清水さんは、このコロナ禍を通して、初めて「ラテン気質」が何であるのかに、気づいたという。
「第一に、それは家族、とりわけお年寄りを大事にする文化などだと思う。州政府の指示を守るのも、お年寄りに感染させたり、死なせたりしたくない、という気持ちが根底にあるからだろう。そして第二は、明日よりも今日を大切に生きる、ということ。ラテンの人々は『いい加減』といわれることもあるけれど、彼らがこれだけ厳しいロックダウンを守っていることに、心底驚きました」
バルセロナから見た日本
バルセロナに長く住んだ清水さんの目に、日本のコロナ対策はどう映っているのだろう。
「一番気になるのは、各国に比べ、日本では最初からPCR検査の数が少なく、今も絞られているように見えることです。市中感染が広がれば、クラスター追跡はすぐ限界にぶつかる。考えたくはないが、許認可権限を握る厚労省がデータを独占し、対策を取り仕切りたい、という意識の表れではないか、と危惧しています」
省庁の縦割りは、あらゆる分野に及んでいる。清水さんは、あらゆる申請を業者に代わって行う「へストール」があるスペインと違って、日本の申請手続きは煩雑過ぎると指摘する。
「いろいろな支援や補助があっても、役所の縦割りで、申請先は違う。しかも、事業者や個人がすべて自分で書類を揃え、提出しなくてはいけない。せっかくの制度を利用しきれていないのではないか」
ジャーナリストの経験から、清水さんは今の日本のメディア状況についても批判的な目を向ける。
「警視庁クラブの経験から言っても、取材源に対してメディアが批判に及び腰になるのはわかる。しかし、日中のワイドショーはともかく、夜の報道番組では厚労省の技官グループや経験者が公的見解を語り、ほとんど疑問をさしはさまず、批判もしようとしない。通常の出来事と違って百年に一度、世界中を変えつつあるパンデミックだという危機感が乏しいのではないでしょうか」
さらに清水さんは、日本ではますますメディアから多様性が失われている、と警告する。
「スペインでは右派の国民党と左派の社会労働党が主軸になって政権交代を繰り返し、どの政党もメディアを支配しきれていない。地域政党もあって、言論や報道に多様性が確保されている。どのテレビ局を見ても、どの新聞を読んでも同じ、という日本の現状は、やはりおかしいと言わざるをえません」
豆腐店の引継ぎ
実は清水さんは、経営してきた豆腐店を今年1月1日付で笹原淳(47)・絵美(38)さん夫妻に引き渡し、ほどなく帰国する。笹原さんは仙台市で豆腐店を営み、2019年の全国豆腐コンクールで最優秀賞を得た「日本一の豆腐屋さん」だ。
精神の持続力の衰えを感じた清水さんは、まだ元気なうちに後進に店を引き継いでもらいたいと、2019年暮れから後継者探しを始めた。何人かに打診したが途中で話が流れたため、全国豆腐組合連合会を通して後継者を募集し、笹原さんが応募したという。最後の年はコロナ禍に振り回されたが,その一年を振り返って清水さんはいう。
「コロナ禍は、人間が自然や地球を破壊しながら成長をしてきた帰結の一つ。その意味では、地球温暖化や気候変動とパラレルな現象かもしれない。最近、環境問題で積極的に発言するようになった若者たちの中には、ベジタリアンをさらに進めたビーガン(完全採食主義)に共鳴する人も増えた。ドイツには、台風の名に由来するタイフーン社が世界有数の豆腐工場を操業し、欧州全域に輸出している。アメリカでは大豆、エンドウ豆由来の人工肉が広がり、この勢いは止まらないと思う。その意味で、豆腐には未来がある、と思っています」
日本は欧州の後を追いかけるかのように昨春に第1波が訪れ、政府は緊急事態宣言を出して厳しい行動制限を呼び掛けた。だが、一時の小康状態を経て、やはり昨秋から感染がぶり返し、年明けには再度、緊急事態宣言を出して今に至っている。
第一次の宣言下では、ウイルスの挙動も正体もよくわからず、不安や恐怖がまさっていた。第二次の今、私たちが抱えるのは、ウイルスの脅威そのものというより、もし行動や警戒を緩めれば、再び感染が、ぶり返すかもしれない、という「リバウンド」への不安だろう。かといって、経済・社会活動が停滞すれば、生活そのものが破壊されるかもしれない。そのジレンマが、今の「不安」の正体だ。
今なすべきことは、こうすれば感染拡大を防げるという具体的な指示と、その制限への補償や支援を示し、医療・介護体制をはじめとする、最も高リスクな働き手を支えることだろう。感染が収束した後の景気浮揚策にお金を使うのではなく、今現在、困っている人、立ち行かなくなっている人を救い、支えることだ。そうした社会工学的な抑止策で感染拡大のカーブを抑え、ワクチン接種による社会的免疫のグラフと交差する点に、希望の光がともるだろう。全体の見取り図を示し、「希望」に向かって人心を一つにまとめる。その過程に参画する政治家やメディアの関係者に必要な資質は、「公正」「透明」「信頼性」に尽きる。
清水さんから、日本に先行するスペインの話をうかがって、そんなことを考えた。
ジャーナリスト 外岡秀俊
●外岡秀俊プロフィール
そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員
1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。