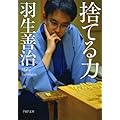打開策は「勝つか負けるかの最前線」で見つかる
この記事に対してネットでは、必ずしも「今度自分も読んでみよう」と関心する人ばかりではなかった。「その程度の本ならエコノミー(クラス)でも読んでるわ」と反発する人もいるし、将棋本や歴史本が好きなのは「単に年寄りだからじゃないの」と皮肉る向きもある。
ただし将棋とビジネスの類似点については、現在3冠(王位、王座、棋聖)の棋士、羽生善治さんが著書「勝ち続ける力」(新潮社)の中で語っている。
共著の柳瀬尚紀氏との対談の中で「駒を動かしていない状況ならば、プラスの手段はたくさんあります。でも、プラスの手を重ねてゆくうちに、いつかある飽和点に来るでしょう。これは、マーケットでも同じことです」と、ビジネスの世界との共通点を述べた。
難解な表現だが、2009年8月19日付の「日経ビジネス」電子版で、記者は羽生氏の主旨をこう解説する。
「効率的に生産し、消費者に届けるというスタイルを確立すればするほど、市場の飽和点は早くなる。新しい商品や情報はたちまちライバル社に研究され、オンリーワンのキラーコンテンツではなくなる。羽生は高度消費社会の現代のマーケットの本質を見抜いただけでなく、新しいモノを生み出そうとする担当者の苦しみ(喜び)に同志的な共感を抱いているのかもしれない」
また羽生さんは、実戦では意外性のある手や局面に向かうことが多いため、「ひらめき」が見つかるケースが多いと明かす。ビジネス界でも「飽和点に達したマーケット」の打開策は、「勝つか負けるかの最前線」でこそ見つかるのではないかと記事では指摘している。