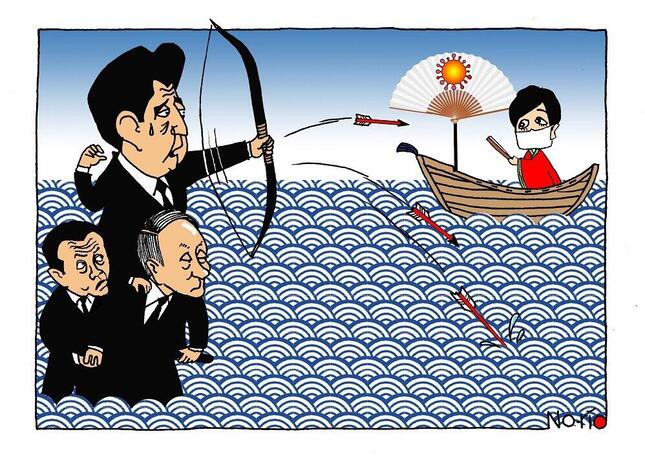安倍晋三首相は2020年8月28日、辞意を表明した。この24日で連続在職日数が2799日になり、大叔父の佐藤栄作氏の記録を更新して憲政史上最長を記録したばかりだった。7年余りに及ぶ看板の「アベノミクス」とは何であったのか。コロナ禍は今後、資本主義にどのような変容を迫るのか。二人の経済学者に「アベノミクス」を総括していただき、今後の経済の展望について話をうかがった。
記憶塗り替える打撃
内閣府が8月17日に公表した今年4~6月期のGDPの1次速報は、物価変動の影響を除いた実質で前期比7・8%減、年率換算では27・8%減の落ち込みになった。
マイナス成長は3四半期連続だったが、コロナ禍が本格化した4~6月期の打撃は特に深刻だった。石油危機後の1974年1~3月期の年率換算13・1%減はもちろん、「100年に1度の危機」といわれたリーマンショックの後の09年1~3月期の年率換算17・8%減を上回る下落幅だ。
下落の一番の要因は、全体の半分以上を占める個人消費の前期比減少率が、過去最大の8・2%になったことだ。これは消費増税のあった14年4~6月期の4・8%を上回る落ち幅だ。
もう一つの理由が前期比で18・5%減になった輸出の落ち込みだ。自動車をはじめ、海外での商品の売れ行きが不振になり、GDPを押し下げた。統計では「輸出」に分類されるインバウンド消費も、3月から5か月連続で訪日観光客数の9割減が続き、ほとんどが消えた。
日本よりも感染が深刻な米国では、同じ四半期に年率換算で約33%減、ユーロ圏も約40%の減を記録しており、打撃は世界規模に広がっている。
立命館大名誉教授・高橋伸彰さんに聞く「アベノミクス」の現在
こうした状況をどうとらえたらよいのか。8月17日、立命館大名誉教授の高橋伸彰さん(67)に話をうかがった。
北海道に生まれた高橋さんは、早稲田大政経学部を卒業後、日本開発銀行(現・日本政策投資銀行)に勤め、1999年から昨年4月まで、立命館大国際関係学部で日本経済論を教え、一時は同大の国際地域研究所長も務めた。日本開発銀行時代には、通産省大臣官房企画室の主任研究官になり、米ブルッキングス研究所で在外研究もした。実務と研究の両方に通じたエコノミストである。
今のコロナ禍による打撃について質問すると、高橋さんはまず、今回の下落要因の約4割が外需の減少によるものだという点に注意を喚起した。
「08年のリーマンショック後は、輸出依存度の高い日本経済の弱点があらわになり、改めて内需への転換が急務だと叫ばれた。しかし、民主党政権においても、また7年以上続いたアベノミクスによっても、その内需転換が図れなかった顛末が、今回のコロナ禍で露呈したといっていい。内需のかなりの部分は個人消費が占めるが、その個人消費が増えなかったのは賃金が増えなかったからだ」
安倍晋三政権は2013年6月に発表した「日本再興戦略」で「アベノミクス」の全体像を示した。大胆な金融緩和政策、機動的な財政政策、成長戦略という「3本の矢」でデフレを脱却するという青写真だった。
大規模な金融緩和によって企業業績を伸ばし、賃金を増やして消費を喚起し、それがさらに企業業績の拡大をもたらすという好循環を作り出し、デフレを克服するという見取り図である。
だが、雇用者に支払われる賃金の総額は1997年をピークに安倍政権が誕生する直前まで減少を続けていた。アベノミクスによって、一時、実質賃金がプラスに転じたこともあったが、2018年12月には、厚労省の「毎月勤労統計」が04年から統計方法を変更していたことが総務省の指摘で発覚し、野党が国会で、「アベノミクス偽装」として追及する騒ぎになった。
厚労省が今年2月7日に発表した2019年の毎月勤労統計(速報値)では、名目賃金にあたる労働者1人あたり平均の現金給与総額は前年より0・3%減の月額32万2689円で、6年ぶりの前年割れとなった。正社員より賃金が低いパートタイム労働者の比率が高まったのに加え、働き方改革などを受けて労働時間が減り、全体の賃金を押し下げた結果だ。7年余りかけても、当初アベノミクスが見込んだ「好循環」は実現していないことになる。高橋さんはこう指摘する。
「派遣やパートタイムなど全体の4割近くを占めていた非正規雇用の労働者がさらに増え、数だけでいえば雇用環境は改善したように見えるが、現実には正社員のベアもほとんど上がらず、その他の手当も増えなかったことから、消費増によるデフレ脱却もできていない。一言でいえば、アベノミクスによって、内需主導への構造転換ができなかったということだろう」
日銀「異次元緩和」の実態
日銀の黒田東彦総裁は、異次元の「量的・質的金融緩和」によってマネーサプライを増やし、物価をあげることを目指した。そのために大規模な国債買い入れ、マイナス金利、長期金利操作など、さまざまな緩和策を打ち出してきた。
高橋さんの見方によれば、黒田総裁は、「貨幣量さえ増やせば物価は必ず上がる」という極端な「リフレ派」ではなかった。就任時の挨拶でも、デフレの原因は多様であり「あらゆる要素が物価上昇率に影響している」と述べ、「リフレ派」とは一線を画していた。
ただ、物価安定の責任論に話題が及ぶと一転して「どこの国でも中央銀行にある」と主張し、「できることは何でもやるというスタンスで、2%の物価安定の目標に向かって最大限の努力をすること」が日銀の使命だと言い切った。
これに対し東大名誉教授の吉川洋氏は、2017年に、「4年以上マネーサプライを増やし続けても2%の物価上昇を達成できない『実績』を見れば、リフレ派の理論は『否定』されたも同然だ」と指摘した。
実際、黒田総裁が当初掲げた「2年程度でインフレ目標2%達成」という目標の達成時期は7回も先送りされ、2018年2月に発表した「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」では、「2%インフレ目標」の達成時期の文言すら削除されるに至った。
ではなぜ、日銀の展望通りに物価が上昇しなかったのか。それは日銀が説くように人々のデフレ願望が根強かったからではない、と高橋さんは言う。
「吉川氏が指摘するように、リフレ派の物価理論は間違っていた。日銀が目標に掲げる物価指数とは、現実に存在し観察できる物価ではない。個々の財やサービスの価格を加重平均して計算される統計データだ」
それでは物価指数の基になる個々の財やサービスの価格はどのように決まるのだろう。
「吉川氏によれば、大多数の価格は生産費用をベースに生産者が決め、その価格を消費者が『公正』と認めれば、現実に価格は変動し物価指数も変わる」
つまり、鍵を握るのは賃金をはじめとする生産費用であり貨幣量ではない。日銀が貨幣量を増やしたからといって価格を上げる生産者はいないし、そう言われて値上げを受け入れる消費者もいない。
「生産者が価格に転嫁せざるを得ないほどに、また、消費者が値上げを認めても良いと思うほどに、賃金や原材料価格が上がらなければ、個々の物価も、その加重平均である物価指数も上昇しない」
笛吹けど踊らず。日銀の思惑が外れた理由について、高橋さんは吉川さんの説を引きながら、そう説明する。
緩む財政規律
この間、日銀は国債を買い続け、2019年末時点で485兆円の国債を保有するまでになった。これは政府の国債発行残高の47%を占める数字だ。日銀は、「政府による財政資金の調達支援」という「財政ファイナンス」ではないという立場を取り続けているが、もはや日銀による買い支えがなければ、税収の約2倍もの予算すら組めない状況になっている。
今年度の一般会計は160兆円と、すでにGDPの約3割に上っていた。もともと国債を頼りに予算を組んでいたところに、コロナ禍の打撃が加わり、政府は2度の補正予算で年間税収に近い計57・6兆円の追加財政支出を伴う対策を決めた。財源は国債の追加発行で賄うしかない。今年度の新規国債発行額は前年度の2・4倍、国債残高は今年度末で964兆円になる見込みだ。
ふつうなら考えられない構図だが、空前の財政運営を支えるのはやはり日銀だ。日銀が大量に国債を買い進めるため、国債の金利は「ゼロ」近くに抑えられる。ふつうなら国債発行による金利上昇への懸念が借金のブレーキになるが、「異次元緩和」のもとではそのブレーキも、利きにくくなっている。
日銀は4月には国債買い入れの上限を撤廃し、5月には麻生太郎財務相と日銀の黒田総裁がコロナ禍に「一体となって取り組む」という共同談話を発表して政府・日銀の協調姿勢を示した。中央銀行の「独立性」は、もはや名ばかりになったかのようだ。
「かつての金利水準なら、1千兆円の国債を発行すれば、50~60兆円もの支払い利息を覚悟しなければならなかったのに、ゼロ金利のもとでは、過去の債務にかかる利息を含めても10兆円に満たない。新規に発行する国債の利払いは限りなくゼロに近く、財務省は金融緩和のメリットを感じているだろう。しかもドル建てやユーロ建てで国債を発行しているならデフォルトの恐れも出てくるが、円建てなら円を刷り続ければ、発行済みの国債は返済できる。また、すでに発行済みの国債については、10年ごとに残高の6分の1を返済し、残りの6分の5を借り換える必要があるが、それも日銀が最終的に買い取ってくれるなら、クリアできる」
では問題はないのだろうか。高橋さんはこう指摘する。
「財政規律が緩むだけではない。金利を低くすれば、市中の人は金を借りやすくなると思うのがふつうだろう。しかし、金利が低くなればなるほど、銀行はリスクを取れなくなる。実際、金利が5%なら、100社にそれぞれ100万円を融資して、そのうち5社が返済不能になっても、銀行は残りの会社からの利息収入で回収不能になった損失分をカバーできる。だが金利が1%に下がれば、2社が返済不能になると、もはや銀行は利息収入で損失をカバーできない。つまり、金利が下がると銀行のリスクを取る能力は低下する。この結果、金利を高くしても借り入れ需要があり、しかも、手っ取り早く回収できる株や土地など、投機的な方面に融資が向かいがちになる。これがバブルの始まりでもある」
日銀は、民間の金融機関から国債を買って市中にマネーを供給し、企業活動に金が回るようにするといってきた。だが現実には企業活動に回らず、株や土地に向かって物価ではなく資産価格の高騰を引き起こしている、との指摘だ。
「失われた20年」
実務家として、研究者として戦後の日本経済を見守ってきた高橋さんは、歴代の自民党政権が一貫して「成長」を最優先の課題にすえてきたのではない、という。たしかに、岸信介首相を継いだ池田勇人首相は「極大成長」を最優先とする「国民所得倍増計画」を掲げて、10年で国民所得を倍に増やすと謳った。しかしその後は、佐藤栄作首相の「中期経済計画」から小渕恵三首相の「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」まで、30年以上にわたり日本の経済計画では成長よりも、むしろ成長による歪みの是正や、福祉の充実および国民生活の豊かさなどが優先的な目的として掲げられてきた。
「成長」が、再び最優先の政策課題になったのは、2001年の小泉政権以降だという。だが、規制緩和や構造改革の掛け声にもかかわらず、バブル崩壊後の「失われた20年」が続いた。その長い停滞を打ち破ろうと、「成長」の旗を受け継いで華々しく登場したのが「アベノミクス」だった。
たしかに円安が進んで輸出企業の追い風になり、株価は急上昇した。しかし、その後も日本経済をリードするような成長産業は育たず、閉塞感はより強まったように思える。
内閣府は今年7月30日、2012年12月に始まった直近の景気拡大が18年10月に終わっていた、と認定した。政府は19年1月に「今回の景気回復は戦後最長になったとみられる」と発表していた。02年1月から08年2月まで73か月続いた「いざなみ景気」を超えるとの強気の見通しだったが、実際はコロナ禍が始まる前に71か月で記録がストップしていたことになる。昨年春ごろから、民間では景気は山を越えたとの見方が広がっていたが、それを裏付けたかたちだ。
高橋さんは、アベノミクスを振り返って、次のように言う。
「必要なことは、大胆な金融緩和よりも、雇用の悪化で失われた所得の回復だった。アベノミクスは企業の資産を増加させたが、それが好循環にはつながらなかった」
賃金は、個々の企業にとってはコストだが、国内経済にとっては購買力である。賃金が増えなければ消費は増えず内需も増えない。日本でもデフレが始まる90年代後半まではベア主導型の賃上げが主流で、「日本的経営」が健在だった時期は、経営者も賃金を購買力ととらえる傾向が強かった。
GDPの6割近くを占める個人消費を支えているのは、中間層を含む庶民の毎日の消費だ。その「水位」を上げるには、賃上げをはじめとする所得の増加で家計の懐をあたためることが欠かせない。
日経平均で株価が4000円以上、時価総額で100兆円増えても、消費は2兆円しか増えない。その結果高級品が売れたとしても、一回限りで終わり個人消費への波及効果は乏しい。だが、家計の所得が10兆円増えれば、消費支出は持続的に8兆円増える。
デフレが生じたのは、賃金が上がらず家計が日々の消費で、より安いものを求めた結果、国内の物価が下がり続けたためで、日銀の金融緩和が不足していたからではない。
だが、企業は純資産を増やしたのに、なぜ90年代後半から賃金は減り続けたのか。高橋さんは、90年以降、銀行と企業の間の株式の持合い割合が減る一方、外国の法人や機関投資家の比重が急速に高まり、株主の利益を優先するアメリカ型の企業統治が蔓延(はびこ)るようになったことが背景にあると指摘する。
バブル崩壊後、日本企業の株式の3割以上を外国人が所有し、株価の値上がりと配当を要求する株主の声が強まった。その結果、企業は賃金を削り、内部留保を貯め込んで、上場企業の半分が実質的な無借金経営を誇るまでになった。
資本主義における企業本来の役割は、家計部門からお金を借り、それを人材育成や機械設備、研究開発に投資して利益を上げ、その収益を賃上げや配当で家計に還元し、経済の好循環をリードすることにあった。家計から金を借り、賃金や配当で家計に還元する成長のエンジンであるはずの企業が、いまや家計よりも金を貯め込む「貯蓄主体」になってしまった。
「経済思想史家のロバート・ハイルブローナーは、『無借金経営を誇るような経営者は現代の地主である』と言いました。これでは、成長のためにリスクを取る、という前向きの挑戦はできなくなってしまう」
日本では企業がプラットフォームづくりに参加したのは、家電でいえばビデオ規格のVHS、自動車でも省エネ車までで、情報通信の世界では後塵を拝してきた。
「日本は常に、自分たちより一人当たり所得が上の欧米の先進諸国を目標に、欧米で使われるモノを少しでも品質が良く、しかも安く作ろうとしてきた。しかし今成長しているのは新興国や発展途上国。中国や東南アジアに入り込んで新たな市場を開拓する、という発想に欠けていた」
米国は90年代から知的財産権を強化してプラットフォームを独占し、追随を許さないようにしてきた。「真似できない」のではなく、制度的に「真似をさせない」堡塁を築いたのだった。
この間、液晶のシャープ、プラズマのパナソニックなど、日本の電機産業が「集中と選択」で行った設備投資の多くは、市場を開拓できずに失敗に終わった。
「3本目の矢」が成果をあげられなかったのは
アベノミクスで「3本目の矢」とされた「成長戦略」は、企業の競争力を強化し、民間投資を喚起するという施策で、健康、エネルギー、次世代インフラ、農林水産業に重点が置かれた。しかし原発輸出、インフラ輸出など、経産省が旗を振ってきた成長戦略の柱は、ほとんど目ぼしい成果を収めていない。
「私もかつての通産省に3年いたが、後発国の優位性が残る60年代までは、『国策』としての産業政策にも意味があったかもしれない。かつて大蔵省が『官庁の中の官庁』として君臨していた時代には、抵抗勢力として通産省の存在意味もあった。しかし財務省が財政の手綱を引き締められなくなってから、その独走ぶりが目立つ。国策会社のジャパンディスプレイの失敗などを見ると、もう『国策』に右へ倣え、という旧来型の路線は終わりを迎えていると思わざるをえない」
高橋さんが危惧するのは、安倍政権の経済政策決定の過程で、自らの政策に都合のいい専門家で身内を固める傾向があることだという。
「これは構造改革に批判する人すべてを『抵抗勢力』と位置づけた小泉政権から続く姿勢だろう。私は、NHKの『日曜討論』で、『骨太の方針』を決める経済財政諮問会議にも、正式の議員として労働組合の代表を入れてはどうか』と提言したが、当時の甘利経済再生相からは『経済財政諮問会議は政府の経済政策を審議する場だ。労働組合の代表には必要なときに話を聞けばいい』と一蹴された。日銀の金融政策審議委員会のメンバーも、安倍政権になってからは、ほぼ全員リフレ派で固められ、異論は出にくい。これではアベノミクスがTINAになってしまう」
「TINA」とは2015年4月、安倍首相が米国の上下両院合同会議の演説にあたり、構造改革の重要性について触れる際に使った言葉だ。「There is no alternative」の頭文字を取った略語で、もともとは英国のサッチャー首相が議会演説で多用した、とされる。「ほかに選択肢はない」という意味で、「この道しかない」とも訳される。強い決断を示す言葉だが、独善に陥る危うさと紙一重でもある。
「経済政策は、つねにもう一つの選択肢を持ちながら、結果を見て修正し、改善していかねばならない。他の選択肢について聞かない、聞く耳を持たないというのなら、現在の政策が間違っていても、その誤りを認めないという独善につながるのではないか」
高橋さんは、そう警告する。
アベノミクスの7年余、株価は上がり、円安になって輸出企業の収益は向上した。新卒の就職希望者の内定率も上がり、「自分の生活は向上しないまでも、世の中全体の雰囲気は明るくなっている」という意味では、見た目の景気は良かったのかもしれない。
だがコロナ禍で人や社会の動きは止まり、インバウンド消費をはじめ、飲食業、宿泊業、娯楽産業、観光業の需要は「蒸発」した。
テレワークへの切り替えやITのさらなる導入など、新しい需要に目をやれば、新しい市場を開拓する可能性はあるかもしれない。だが、そうした動きから取り残される地域や企業、また、ついていけない人をどうするかが、これからの経済学の課題ではないか、と高橋さんは言う。
「経済学の貧困」に陥った理由とは
高橋さんは2015年4月に、日本記者クラブで「経済学の貧困」と題して講演をしたことがある。高橋さんはその中で、ケインズの高弟である英国の女性経済学者ジョーン・ロビンソンが1970年の講演で語った問題提起を話題の中心に据えた。
60年代後半まで、ケインズ政策の導入は成功を収め、西側先進諸国のGDPは恒常的に拡大を続けた。新古典派は完全競争の成立に必要な4つの前提条件が整えば、政府が関与しなくても個人の利益と社会の利益が最大化すると唱えたのに対し、ケインズは、雇用量は経済全体の有効需要によって決まると考え、経済政策による政府の関与の必要性を唱えた。その考えは英国から米国へと広がり、戦後の西側諸国において経済政策の基盤になっていた。
だがロビンソンは、70年の講演で、ケインズが正面から向き合わなかった「貧困」や「格差」の問題にも経済学は応えるべきではないかと訴えた。
新古典派は、次のような条件を前提にしていた。
「生産手段の私有制」
「各経済主体は経済合理人として自らの経済的利益を最大化するように行動する」
「生産要素の使途は私的・社会的費用をかけずに自由に変えられる」
「経済的な利害は市場機構の調整によって解決される」
ロビンソンは、こうした条件を前提としなければ成立しない経済理論は、再考すべきだと指摘した。
だが、そうした問題提起は忘れ去られ、経済学は、「政治家が考える目的に沿って、予算などの稀少資源をいかに配分すれば効率的に目的を達成できるか」という分野に自らの研究対象を狭めていくことになった。実際の自然環境や生活環境といった社会的な条件を考慮して現実の「格差」や「貧困」に立ち向かうのではなく、名目的な所得格差を示すジニ係数や、相対的貧困率の指標といった統計上の数値をどうすれば効率的に改善できるかを政治家に提言する、という学問のスタイルに変節していった。
1970年前後は、日本だけでなく、世界的にも成長が行き詰まり、「成長一辺倒」の世界観から「低成長のもとでの生活重視」「福祉政策のもとでの社会共通資本の充実」「環境に配慮した成長」といった価値観への転換が求められる時期だった。
だが、ニクソン・ショック、石油ショックのあとでは声高な「成長重視」の流れに押し流され、その後は経済的な「新自由主義」、「市場万能主義」の名のもとに、社会が成長を最重視する価値観に戻ってしまった。
高橋さんは、そうした「経済学の貧困」に対し、コロナ禍は再考を迫っていると考える。
「私たちの社会は、もっと早く、もっと効率的にという合言葉をもとに、利益を最大化する方向へ突っ走ってきた。しかし社会には、歩きたくても歩けない人、話したくても話せない人、見たくても見られない人がいる。『プロクルステスの寝台』ではないが、私たちは生きている人間に合わせて経済理論を立てるのではなく、生きている人々を、『経済合理人』というモデルに押し込めようとしてきたのではなかったのか」
経済学は客観的に実証できる範囲に対象を限定し、抽象モデルによって操作できる統計やデータを扱う傾向を強めてきた。定量化できない「貧困」や「格差」、文化人類学が考察してきた「無償の贈与」や「相互扶助」など古くからある慣行は、先進国の経済合理人をモデルとする経済学からは、「学問外」として排除される傾向にあった。
「ジョーン・ロビンソンはかつて、技術開発は、普通の人がどれだけ我慢できるかにかかっている、と言ったことがある。パソコン起動までに3分かかることも我慢できない人が増えれば、企業はその数分の短縮のために膨大な金を使ってまで技術を開発する。しかし、そうやって便利になることが、ほんとうの幸せなのか。利益を最大化することだけを指標に競い合うのではなく、さまざまな個性、能力の人々が集まる社会で、『満足度』を最大化することが、経済学の目的なのではないか」
コロナ禍のもとで、高橋さんはそう考える機会が増えたという。
法政大教授・水野和夫さんに聞く「資本主義の終わり」
いつ終わるとも知れないコロナ禍を前に、グローバル化した資本主義はどう立ち向かい、変容していくのか。これまで世界史を縦軸、現代の経済変動を横軸にとって、精緻な分析をもとに資本主義のありようを論じてきた法政大教授の水野和夫さん(66)に、8月19日、ZOOMでお話をうかがった。
水野さんは早稲田大を経て埼玉大大学院で経済学博士号を取り、現在の三菱UFJモルガンスタンレー証券に入社。同証券チーフエコノミストを務めたあと、2010年に内閣府大臣官房審議官、翌年に内閣官房内閣審議官を経て16年から法政大で教鞭をとってきた。実務、行政、研究の各方面で鍛え抜かれたエコノミストだ。
昨年2月、水野さんは母校の愛知県立旭丘高校の同窓会「鯱光会」で「資本主義の終焉と歴史の危機」と題する講演をした。
その中で水野さんは、歴史家ヤーコブ・ブルクハルトが「世界史的考察」で指摘した三つの「歴史の危機」を引用し、現代を「4度目の危機」と定義した。
「歴史の危機」とは、「既存のシステムが崩壊し、機能不全に陥っているが、いまだ新しいシステムの姿、形が見えない状況」を指す。ブルクハルトは、「ローマ帝国崩壊後、カール大帝の戴冠式まで」、「ビザンチン帝国崩壊で中世が終わり、ウエストファリア条約で近代の国民国家が形成されるまで」、「フランス革命などを経て絶対王政が倒され、市民社会が到来するまで」という三つを、「歴史の危機」の例にあげた。
では、なぜ今が「第4の危機」といえるのか。水野さんは、平成の時代が日本ではバブル崩壊、ドイツではベルリンの壁崩壊に始まり、日独が史上初のゼロ金利で幕を閉じることが、象徴的だったという。冷戦期に、互いに生産力増強を競い合った東西陣営の対立が終わり、ふと気づけば、世界は「過剰・飽満・過多」の状況になっていた。
日本では年間40億着の衣類を生産して10億着を廃棄し、食品産業は1~2割の商品を廃棄し、住宅メーカーは13%の空き室率なのに毎年100万戸の新興住宅を建設している。
10年もの国債利回りが日独でゼロにまで低下したのは、「生産力増強の時代」が終わったことを意味する。つまり、ここでの「ゼロ金利」は意図的な金融政策というより、「実物投資によって雇用と所得が増加し、国民の生活水準が向上する」という近代資本主義の限界、システムが飽和点に達したことを示している、という。
資本を自己増殖させるシステムが「資本主義」であり、利子率は資本主義の成績表だ。13世紀以来、世界で最も低い金利を経験した国は、800年の歴史で、わずか6か国しかなかった。複数年にわたって長期国債利回りが2・0%を下回ったのは、過去に、1611年から11年間続いたイタリア・ジェノバしかなかった。
では、繁栄するグローバル資本主義のもとで、なぜこんな現象が起きているのか。水野さんはこう指摘する。
「世界史は蒐集(コレクション)の歴史です。13世紀になるとヨーロッパで従来とはまったく違う都市が現れた。最下層から商人が誕生し資本が都市に投下され、以来現在にいたるまで都市の資本は利潤率(利子率)の高い地域に再投資され、西欧文明と資本主義を世界中に広げっていった」
資本の増加率を測る尺度が利子率だ。「世界史は利子率の歴史である」と水野さんはいう。今でいう「資本」に近い「利息のつくお金」という概念が生まれるのは13世紀のことだ。以来、金利急騰は財政破綻のサインを意味していた。では、これがゼロに近づくということは、何を意味しているのか。
「ROE革命」で貯め込む
本来、「実物投資空間」の利潤率は、国債利子率と連動し、代替できるのが原則だった。
企業はお金を借りて事業を行い、得られた利潤から金利を払う。利潤と利子の源泉は同じだ。違いは利潤が事後的に発生するので、偶発性があるのに対して、利子は事前に契約することで発生し、恒常性があるという点だ。だが長期的に見ると、利子率と利潤率はほぼ連動する。長期金利の目安になるのが10年国債の利回りということになる。
ところが、実物投資によって資本を増やすシステムが限界に近づいた米国は、経済的に支配下にある外国から多額の利子・配当を得て優位性を保とうとした。
その仕組みを支えたのが、米国発の「ROE」(自己資本利益率)革命」だ。これは「ReturnofEquity」の略で、「当期純利益/自己資本」で算出される。これは株主資本の増加率を示し、これが高ければ高いほど資本の自己増殖が加速する。経産省は2014年8月に報告書(「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築」)を公表し、この「ROE」を「最低8%」にまで高めることを推奨してきた。
「この報告書には雇用者の生活向上という視点はまったくありません」と水野さんは言う。
それを側面から支えてきたのが、日銀による「ゼロ金利」と「量的緩和政策」だった。
企業は、銀行や株主から融資を受け、その活動で得た利潤を賃金や利払い、投資へと振り向ける。だが、利子率と利潤率が乖離してしまえば、本来払うべき利払いを大幅に引き下げることができる。もちろん、その反面、家計の担い手である一般の個人は、金融機関に預金をしてもほとんど利子がつかない状態が続いた。
もう一つ、資本の増殖率を高めるために採用したのが、人件費の「変動費」化である。これまでは、売上高から変動費と固定費(人権費)を除いた営業利益が調整項目だった。だが、最終的な利益が絶対に確保しなくてはいけない目標として「固定費」化すると、どこかで調整するしかない。つまり人件費を減らすことによって、企業利益を増やす方法だ。
こうして、この間に企業は、支払うべき利払い、賃金を減少することで得られた膨大な利益を、「内部留保」という形で貯め込んできた。
それには、背景がある。
バブル崩壊後の1997年から翌年にかけ、山一證券、北海道拓殖銀行、日本長期信用銀行などが次々に破綻した後、企業の間には「貸し剥がし」「貸し渋り」に走る金融機関に対し、「もう頼りにできない」という空気が生まれ、資金を貯め込んで自己防衛する傾向を強めた。こうした「守り」の姿勢が、株高による企業の好調と、それとは裏腹の家計への圧迫を招いた。
念のため改めて書くと、こうしたことは、すべて「コロナ禍以前」に、水野さんが指摘していたことだ。
非常事態に備える名目でためた「内部留保」を今こそ危機対応に
インタビューの冒頭で、水野さんはこうした論点を指摘したうえで、まず、「コロナ対応では内部留保を活用すべきだ」という持論を語った。
「この間企業はずっと、いざという時に備えて従業員に、『もうちょっと我慢をしてほしい』と頼み、内部留保を貯め込んできた。緩やかに労働生産性も上がっていたのに、従業員が賃下げにも耐え、非正規雇用を増やしてきたのも、いつか来る『非常事態』に備えて、という名目があったからだ。今のようなコロナ禍で金を使わないというのなら、いったい、いつ使うのか」
もしこのコロナ禍で内部留保の資金を使わないなら、「非常事態に備えて」という建前がウソであったのか、あるいはマルクスが「資本論」で引用した「わが亡きあとに洪水よ来たれ」のように、従業員の命や健康にはまったく顧慮しない資本の論理を貫いているのか、どちらかではないか。水野さんはそういう。
マルクスは同じく「資本論」で、「将来の人類の衰弱や、結局はとどめようのない人口減少が見込まれるからという理由で資本が実際の運動を抑制するというのは、いつか地球が太陽のなかに落下する可能性があるという理由でそうするというのと、どっこいどっこいの話である」と書いた。
水野さんはこの文章の意味をこう解釈する。
「地球が太陽に吸い込まれでもしない限り、資本家は金儲けをやめない。社会にどれほどの危機が迫っても、資本は生き延びるという論理を指した言葉だろう」
水野さんは、政府によるコロナ対応が遅い今、これまで企業が積み上げてきた460兆円に及ぶ内部留保金を活用するべきだという。
「これは企業がまさかのときに備えて貯め込んでいたお金です。いまがその『まさかのとき』でしょう。いまこそ内部留保金を使うべきです」
日本の企業の内部留保は、460兆円に上るが、1999年以前のペースで貯め込んでいたとすれば、200兆円ほどだったろう、と水野さんは言う。
「差額の260兆円は、今回のような非常時に備えていたはずです。もともとこの内部留保には、本来なら従業員に払うべき賃金、金融機関に戻すべき利払い分の計130兆円分も含まれている。これら130兆円は本来『緊急事態対応預り金』として負債の部に計上すべき性格のものです。もし130兆円を取り崩して活用できれば、人口1億2千万人に100万円ずつ、1世帯に247万円を配ることもできる。世帯収入の中央値は437万円(厚生労働省「2019年の国民生活基礎調査の概要」)なので、半年ほどは国民の生活を支えられる。もし260兆円を取り崩し、生活の苦しい人約半数の国民に支給するとすれば、コロナ禍が続いても2年間は危機に耐えられる」
ここまで内部留保を貯め込んだ国は日本しかない。政府が「打ち出の小づち」のように国債発行に頼り、最終的にツケを国民に回すのを待つより、率先して危機に立ち向かうことで、企業の社会的評価はあがる、と水野さんは言う。
メガロポリスの脆弱性
今回のコロナ禍で水野さんが注目するのは、「メガロポリス」の脆弱性だ。
「資本は文明の別名にすぎない」。水野さんは、マルクスが『経済学批判要綱(草案)』で紹介した英国のジョン・ウェードの言葉を引いて次のように話す。
資本がつくった都市文明の頂点に君臨するのがメガロポリスだ。「メガロポリス」は、かつての大都市や首都といった「メトロポリス」を超えて、大都市が帯状に連なる巨大な居住圏、行動圏だ。ふつうの、「メトロポリス」なら半径50キロ圏内だが、それをさらに超えて広がる大都市連鎖空間ということになる。
たとえば日本では、新幹線を通して結びつく首都圏、中京圏、関西圏。コロナ禍はこの1都2府5県で感染者が6割台になり、今は7割を超えている。東京都だけを「Go Toキャンペーン」から外せば、感染が抑えられる、という話ではない。
日本だけを見ると、「単に人口が集中しているから」と言えないこともないが、世界を見渡せば、それが偶然ではないことがわかる。
「ニューヨーク、ボストン、ワシントンのメガロポリスを見ると、第1波のピーク時で感染者は全米の3割、死者は5割。コロナ禍がメガロポリスに集中していることがわかります」
そもそも、都市と資本には、切っても切れない縁がある。そう水野さんはいう。都市の形成は11~13世紀ごろで、初期の資本の概念が生まれたのも13世紀ごろだ。
「都市は人口を集積し、資本を集中し、上へ上へと伸び、横にも結び付いて巨大なメガロポリスを形成した。その意味で、13世紀以来の都市集中の累積結果が、今回のコロナ禍で直撃を受けたのだと思う」
今後、コロナ禍のような感染症を防ぐには、再び都市のサイズを50キロ圏内に戻して分散し、「地方分権」に向かうしかないだろう、と水野さんはいう。
都市に限らず、今回のコロナ禍は、これまで膨張を続けてきたグローバル資本主義に限界を突きつけ、変容を迫っている、と水野さんはいう。
ITは起爆剤になりうるのか
20世紀後半から、次代の産業の中心はITだといわれてきた。最初の資本家である商人は、遠くの町に行って人より早く仕入れ、それを売りさばくことで利益を得た。それ以来、資本主義は「より速く、より遠くへ、より合理的に」をモットーに効率性を求め、消費者には利便性を提供してきた。そのためのツールとして、「次世代のイノベーションの起爆剤」という期待を担って登場したのがITだった。
だが、ITは電気や車の発明と比べ、人類を飛躍的に向上させる技術なのだろうか。水野さんはコロナ禍が問題になる前の昨年、新聞で読んだ米国の経済学者ロバート・ゴードンのインタビューが忘れられない、という。「長期停滞論」を唱え、「もはや輝かしい過去の再現はあり得ない」というゴードンは、次のように語った(2019年6月6日付け朝日新聞電子版)。
「エジソンが電灯を発明したのは1879年ですが、第2次世界大戦前には米都市部のほぼ全世帯に電気が届きます。製造業の動力も蒸気機関から電気に代わり、経済の効率が劇的に上がりました。電灯とほぼ同時期に発明されたエンジンが、自動車や航空機を動かすようにもなりました。こうした発明を土台に、1970年までの半世紀は、毎年ほぼ3%のペースで生産性が伸び続けました」
ゴードンはそのころまでに、ほとんどの発明は出尽くし、今後はかつての電気や車に匹敵する新たな技術は生まれないだろうという。たしかにデジタル化で暮らしは便利になり、娯楽や通信の世界は格段に便利に、豊かになった。だが、それは暮らしに必須のものなのか。そう自問してゴードンはいう。
「ビル・ゲイツが生み出したものは偉大だが、電気には及ばない。どの発明も一度限りですが、重要度には大きな差があります。屋内トイレや空調のない世界か、スマホのない世界か選べと迫られれば、みんなスマホを諦めるのではないですか」
水野さんは、このインタビューを読んで、かつて證券会社に勤めていた当時を思い出した。携帯電話のない時代、地方に出張に行けば先輩や同僚に食事に誘われ、しばし仕事を忘れることができた。だが携帯電話を持たされると、地方に行っても仕事に追われ、電子メールが普及するようになると、その夜のうちに宿泊先のホテルで報告書を書くことを命じられるようになった。
「そのころから、プライベートの場に仕事が忍び寄るようになった。ITは日本ではもっぱら労働強化に使われ、人はますます不自由になっているのではないでしょうか。このうえ、政権がいうように『ワーケーション』という働き方が導入されたら、まったく余暇はなくなってしまう」
ケインズは1936年の「雇用・利子および貨幣の一般理論」やその他の論文で、2030年には、「人間の創造以来初めて、資本を増やさなければならない、という状況から解放される」と予見した。水野さんは言う。
「資本を増やすには、節約をして、貯蓄と投資をしなければならない。そうしたことから人類は初めて解放されるだろう、とケインズは言った。資本を増やす必要がない、ということは、ある意味ではゼロ金利の時代ということだろう。実は、そうした社会は、今日の日独でもすでに実現している」
だがケインズの主張の力点は、経済上の逼迫から解放されて、それをいかに利用するのか、ということにあった。
「経済上の逼迫とは、資本不足のことで、具体的には、資本不足で供給力が足りず、食べるものも、着るものも、住宅もない、死んでしまうかもしれないという状況です。この状況から解放されて、人間は真に恒久的な問題を考えなくてはならない。それは、余暇を賢明で快適で裕福な生活のために、どのように使えばよいのか、ということだ。ケインズはそう問題提起したのだと思う」
コロナ禍以前、政府の働き方改革は、依然として「生産性向上」を目指していた。「より速く、より遠くへ、より合理的に働け」という考え方だ。
「ケインズは、将来は、労働時間を3分の1程度に減らせると予見し、浮いた時間をどう充実させるかを考えるのが、課題だといった。そして、ゼロ金利時代になっても貨幣愛に捕らわれ、働け働けという人がいたら、病院にでも行った方がいい、とまで言っている。コロナ禍後の私たちが目指すべきなのは、成長至上主義と決別し、『よりゆっくり、より近く』へと価値観を切り替えることなのだと思います」
水野さんは、「資本の誕生以来、その蓄積には不正すれすれの行為もあったはず』だと指摘してこう言う。
イギリスの資本家第一号は海賊のドレークだし、イタリアのメディチ家はギャングの家系である。資本の過剰を示唆しているゼロ金利が実現した日本では、ようやく1930年にケインズがいった「少なくとも100年間、自分自身に対しても、どの人に対しても、公平なものは不正であり、不正なものは公平であると偽らなければならない。」と姿勢を続ける必要がもはやなくなった。
「これまでは人類が偽ってきたのは、『不正なものは有用であり、公平なものは有用でないから』だとケインズはいう。同じことをシェイクスピアも『マクベス』で3人の魔女に『きれいは汚い、汚いはきれい』という有名なセリフで言わせている。資本の蓄積には不正も働くが、国民生活の向上につながるなら有用だから大目にみよう。しかし、資本が過剰になれば、ケインズは『不正は不正』とみなすべきだと主張していた。だから、『財産としての貨幣愛は半ば犯罪であり半ば病理的な性癖』とまで言った。内部留保金の一部は負債としての性質をもっているにもかかわらず、資本の部の計上しているのは不正ではないが、信義則違反だろう。現在の日本は、賃下げをしてまで資本を蓄積する必要はないはずです」
水野さんの厳しい指摘は、経営者にとっては耳に痛く響くだろう。だが、コロナ禍という、経験をしたことのない大きなうねりを前にして、惰性で運航したり、自動操舵に身を任せることは、もうできない。その真摯な諫言を、「アフター・コロナ」に目指すべき指針と受け止めるべきではないだろうか。
エコノミストお二人の話をうかがって、まったく違う体験、思考経路をたどりながらも、今あるシステムの限界を確信し、来るべき社会へのビジョンを模索する点で、お二人は同じ地平に立っていると感じた。
ジャーナリスト外岡秀俊
●外岡秀俊プロフィール
そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員
1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。